効率の追求
丼碁(ザル碁)と囲碁を考える
碁にもいろいろありますが、本質は同じです。
| さて、いよいよ囲碁です。勝敗の判定方法以外は、囲碁も丼碁(ザル碁)や純碁と基本的には同じです。 丼碁(ザル碁)と囲碁のルールの違いを確認しておきます。 共通ルール。 ・碁盤に引かれた線の交点に、黒白交互に石を置く。 ・一度置いた石は動かせない。 ・相手の石を囲めば取れる。 ・コウはすぐに取り返せない。 丼碁(ザル碁)の勝敗判定ルール。 ・石を沢山取った方が勝ち。 囲碁の勝敗判定ルール。 ・地を沢山取った方が勝ち。 「地」という言葉がここで初めて出てきました。 純碁との比較で使った5路盤の実戦例で考えます。 |
図4-9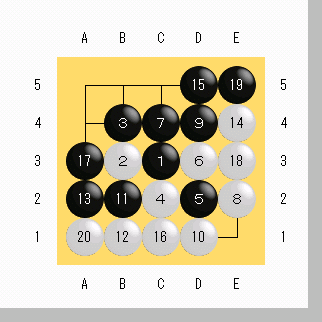 |
囲碁では、この白20まででお終いです。 黒も、もうこれ以上打つ必要はありません。 |
図4-10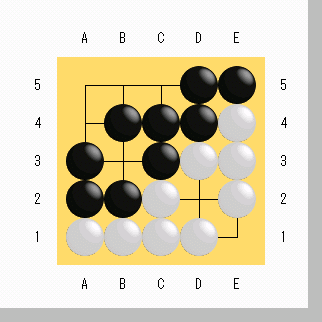 |
ルールで出てきた「地」について、まだ何も説明していませんでした。 黒の地とは、黒石に囲まれた空点の集まりのことです。 白の地とは、白石に囲まれた空点の集まりのことです。 |
図4-11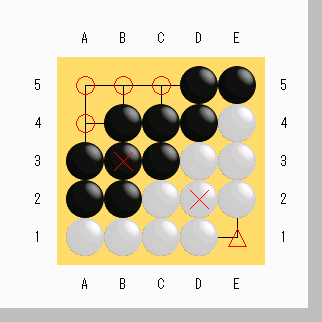 |
そして、地を数える時は、それまでに取られている石を埋め戻してから数えます。 黒は地を4個取りました。 白は地を1個取りました。 地の多い方が勝ちですから、黒が3個勝ちました。 |
図4-12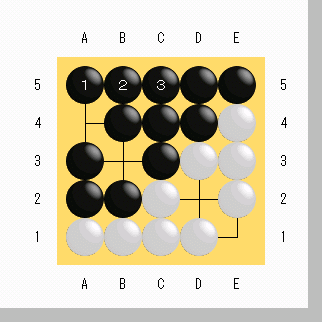 |
これは丼碁(ザル碁)での最後の手続きですが、黒は1から3を打つことで白石を3個得ます。 つまり、黒専用の空点と白専用の空点の、数の差だけ、白石を得たわけです。 そこに途中で取った石を加え、相手との多少を計算して勝敗を決めています。 これって、結局図4-11で、地の数を比べているのと同じ事ですよね。 |
| 念のため、数式を使って確認しておきましょう。 その前に、いくつか数式用の言葉を作ります。 黒空点 : 黒が置くことができる点(白が置いても結局取られてしまう点) 白空点 : 白が置くことができる点(黒が置いても結局取られてしまう点) 黒除石 : 囲まれて盤から取り除かれた黒石(丼碁(ザル碁)ではパスのペナルティも含む) 白除石 : 囲まれて盤から取り除かれた白石(丼碁(ザル碁)ではパスのペナルティも含む) [丼碁(ザル碁)の計算] 黒の得点 = 黒空点 + 白除石 白の得点 = 白空点 + 黒除石 得点差 = 黒の得点 - 白の得点 = 黒空点 + 白除石 - 白空点 - 黒除石 = (黒空点 - 黒除石) - (白空点 -白除石) [囲碁の計算] 黒の得点 = 黒空点 + 黒の眼 - 黒除石 白の得点 = 白空点 + 白の眼 - 白除石 得点差 = (黒空点 + 黒の眼 - 黒除石) - (白空点 + 白の眼 -白除石) と、この様になります。 丼碁(ザル碁)の得点差と、囲碁の得点差では、「眼の数」による影響はありますが、上の実戦例の様に眼の数が同じ時には効果が相殺されますので、結果に反映しません。 また、上の例では、パスによるペナルティの関係で、除石の数が影響を受け、丼碁(ザル碁)と囲碁の得点に食い違いがありますが、この際細かいことには目をつぶります。 つまり、 細かいことはさておき、「丼碁(ザル碁)と囲碁の本質は同じ」だということです。 ここで扱った碁盤はとても狭かったので、丼碁(ザル碁)や純碁の最後の手続き(自分の空点を埋め尽くす作業)が大したことはありませんでした。 しかし、これが本格的な19路盤ともなると、結構大変な作業です。 その大変で退屈な作業を省略して、終局時の勝敗判定を効率化したのが囲碁だといえます。 また、この方がよっぽど重要かもしれませんが、 「石を取る事に、気持ちが偏りがちな丼碁(ザル碁)」 や 「石を置く事に、気持ちが偏りがちな純碁」 と比較したとき、 「自陣の広さと奪取する石数の両方に気を配る必要がある囲碁」 の方が、同じ碁の仲間でも、より進化した姿と言えるのではないかと思います。 |
以上で入門講座を終わりますが、最後にこれだけは言いたい。
ポン碁を極める道は、丼碁(ザル碁)や純碁を極める道に直結しています。
そして、丼碁(ザル碁)や純碁を極める道は、囲碁を極めようとする道と全く同じ道だと言えます。
ポン碁は立派な碁の仲間です。大いに楽しんで頂きたいと思います。
入門講座で取り上げるには適当でないと思われるテーマとか、私の碁歴など、囲碁に関するコラムみたいなものを
「勝手読み」コーナーにUPしていきます。
宜しければそちらもお読み下さい。