細かいことが気になって(切り賃)
囲碁が現在のやりかたで地を数えるようになる少し前まで、「切り賃」という考え方がありました。 その意味は、「生きるための眼は地に数えない」という事です。 大抵の地は生きるための2眼が複数の空点に含まれた状態で存在しますが、地を数える時いちいち引き算していたのでは面倒くさいし間違えやすかったであろうと想像できます。 そこで、地の空点を全て数えておいて、後からまとめて引き算していました。 で、幾つ引くかというと、何ヶ所で生きているかを数え、その数を2倍して引き算していました。 しかし、それでもまだややこしいので、生きる為の眼が多い方が少ない方に、その差の分だけコミを出すようになりました。 つまり、相手の石を分断すればするほど、後でコミを沢山もらえる理屈で、この事を「切り賃」と呼んでいました。 具体的には、下図の例では、黒が3ヶ所、白が1ヶ所で生きているので、黒が白に「切り賃」としてコミを4目出します。(3×2 - 1×2 = 4) |
|
例8-1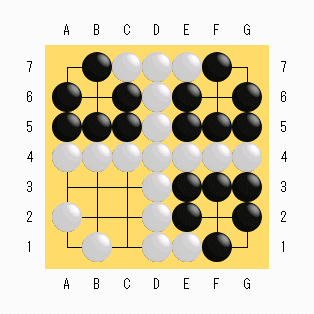 |
では、それぞれの碁のスコアがどうなるか見てみましょう。 黒18手、白18手打ち、次は黒番です。 囲碁はここで終局です。 切り賃付き囲碁の場合は黒からコミが4目出ます。 |
例8-2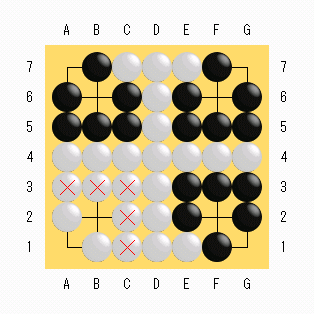 |
純碁と丼碁(ザル碁)では、黒はパスを5回、白は5ヶ所の×に石を置きます。 純碁はここで終局です。 丼碁(ザル碁)はこの後、黒パス、白パスです。 パスに伴うハマとして、黒は白石を1個、白は黒石を6個持って終局です。 |
現在の囲碁は地をそのまま数えます。 黒6目、白7目で、白1目勝ちです。 切り賃付き囲碁では、切り賃4目を黒地から引きます。 黒2目、白7目で、白5目勝ちです。 純碁は盤上の石を数えます。 黒18個、白23個で、白5個勝ちです。 丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。 黒が白石1個、白が黒石6個で、白5個勝ちです。 以上より、このケースでは現在の囲碁以外は同じ結果になります。 ここで扱った7路盤の例では、純碁や丼碁(ザル碁)の終局手続き(つまり自陣に石を埋める作業)は大して負担になりませんが、19路盤ではとんでも無く退屈な作業になります。 その大変な作業を簡略化したのが「切り賃付き囲碁」の計算方法だと考えるのは至極自然です。 そしてさらに、「切り賃」まで省略してしまい、現在の囲碁に至っているのではないでしょうか。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |