うまく説明できない「欠け目」
「欠け目」を国語辞典で調べてみると「必要な連結点を相手に占められているため、目にならない空点。(国語大辞典(新装版)小学館 1988)」と出ていました。 う~む、なるほど。 じゃ、「目」とか「必要な連結点」ってのは何? ってことで、同じ辞典によると「目」は 「連結が完全な石で囲んである一つ、または連結した二つの空点。また、交互の着手によって最終的にそうなる形。個別に二つ以上の目がある一連の石は、イキといって絶対に取ることができない。」 だそうです。 ふむふむ、なるほど。どうやらキーワードは「連結」ですか。 と、ここまでは良いとして、さてこれを人に説明しようとすると・・・。結構、むつかしい。 |
|
図1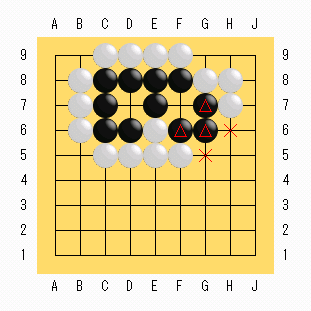 |
「欠け目」は石の死活に絡んで登場する言葉ですね。 例えば左図では、×の呼吸点を白石が占めると、△の黒3子がアタリになります。 そうなると、現在は着手禁止の空点である F7 が、着手可能になってしまい、結局この黒は全部取られてしまいます。 この F7 の様な空点を「欠け目」と言ってます。 辞典の説明にある「必要な連結点」とは、この図では、 E6 とか G8 の点を言うわけです。 |
図2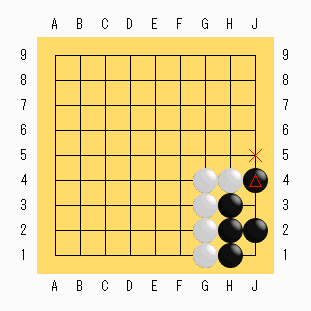 |
辺では左図の様になります。 やはり、×の点に白石が来ると△の黒石はアタリです。従って、J3の点は「欠け目」です。 この黒石は着手禁止点を2個持ってませんから「死」です。 この図で、「必要な連結点」は H4 です。 |
図3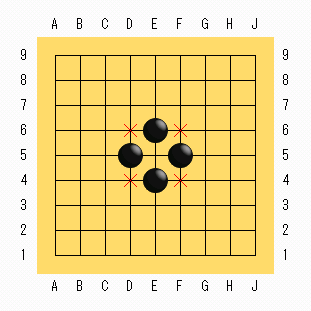 |
左図は E5 を黒4子が囲んでいるため、そこは白にとっての着手禁止点になっています。 しかし、×印が付いた4個の空点の内2点を白に奪われてしまうと・・・、 |
図4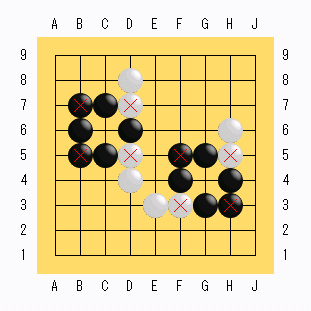 |
例えばこの様に、囲まれた空点の周りにある石の一部がアタリになる可能性が出てきます。 この様な状態になった空点(左図のC6やG4)が「欠け目」です。 この例での「必要な連結点」とは、着手禁止点から見て斜めの位置にある4個の点の内、任意の3点です。 以下、斜めの位置にある点を「カドの点」と呼びます。 |
図5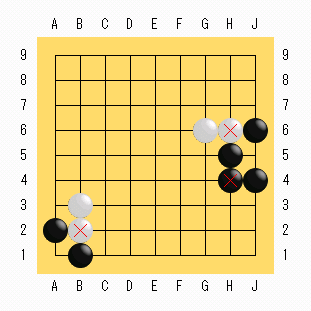 |
入門講座の中で、辺や隅では目が出来やすいと言いましたが、「カドの点」も少ないため「欠け目」も出来やすい理屈です。 辺や隅では、「カドの点」は一つ残らず「必要な連結点」です。 |
図6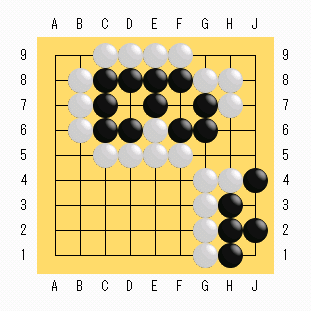 |
さて、図1と図2を一緒にしてみました。 それぞれの石は「死に」のはずなんですが、もし今黒の手番だとすると・・・、 |
図7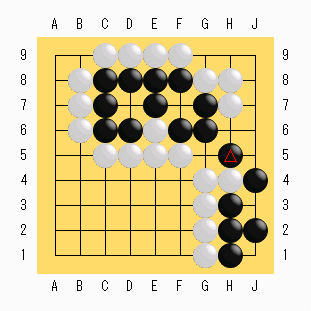 |
△に黒石が来ました。 この1手でアタリにされそうな黒石が無くなっています。 と言うことは、F7やJ3の点は「欠け目」ではなく「目」です。 つまり、この図では H5 が「必要な連結点」と言えます。 |
またまた昔の話で恐縮ですが、図4や図5の形は例外なく全て「欠け目」だと思いこんでいた頃、図7と同じ様な手を相手に打たれ、石が生き返っている事に終局近くまで気が付かなかった思い出があります。 「欠け目」の説明を始めると、大体いつもこんなふうになってしまいます。とても簡潔な説明とは言えません。 そこで今日は皆さんのお知恵を拝借したいのです。 「欠け目」の簡潔な説明方法を教えて下さい。 教えて頂くお礼にプレゼントがあります。下の図は、このコーナーのネタを考えている中で偶然に出来たものです。 黒先でどうなるでしょうか。 |
|
プレゼント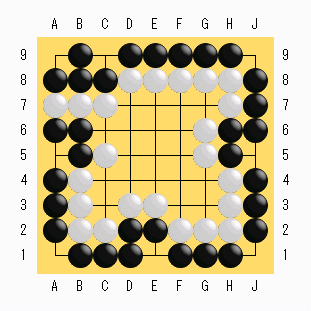 |
いくつか有る変化の中で、今日のテーマにピッタリだなと感じたものを「私の結論」として上げておきました。 (ただし、正解かどうかは全く自信ありません) |
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |