うまく説明できない「手入れ」
先日パソコンと9子局打っていましたら面白い形が出来ました。下の図はその部分だけを9路盤に再現したものです。 パソコン君は左上の死活を間違えまして、おかげで私の5目負けと判定されてしまいました。(もちろん19路盤での話で、下図での判定ではありません。念のため。) で、どうにも悔しくて、「ちゃんと判定しろよ!」と思いつつしばらく盤面を眺めていて、ふと妙な疑問が沸いてきました。 |
|
図1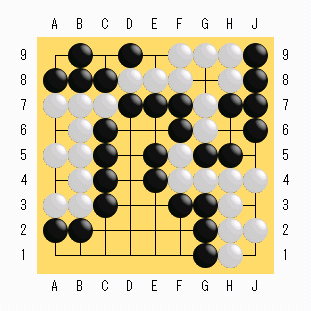 |
パソコン君は、左上の黒と上辺の白が部分的にはセキであるため「活き」と判断したようです。 |
図2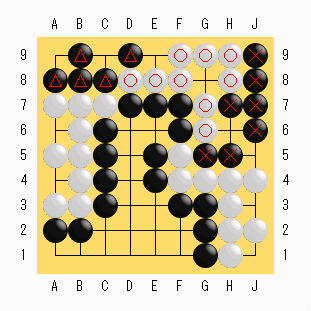 |
しかし正しくは、×印の黒石が死んでいるため、結局セキ崩れで△の黒は「死」と判定しなければいけませんでした。 パソコン君は、×印の黒が「死」であることは正しく認識している様ですが、セキ崩れの判定が出来ていなかったようです。 |
図3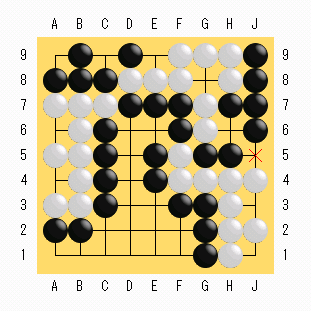 |
さて、私の頭をよぎった疑問は何かと言うと、 「白は×(J5)に打たないよな。だって、打てば1目損だもんな。でも打たなきゃそこの黒を取れないよな。しかし、打たない、損だから。とするとその黒は取られない。じゃ、黒は活きか???」 いや、もちろん死んでますよ。白はJ5に手を入れる必要はない。それは分かってます。 でも、もしこの疑問を誰かから投げかけられたらどう答えたらいいもんだろうか。 |
図4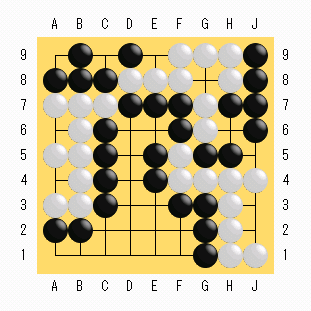 |
ここでちょっと実験です。 右下隅の白石を一つずらしてみました。 この形は白手抜きが出来ません。 |
図5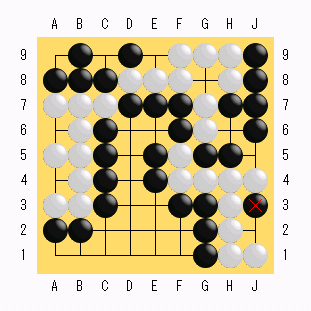 |
もし白が手を抜いていて黒がJ3に打つと、白はJ5に入れない状態になります。 つまり、右辺もセキになってしまいます。 と言うことは、左上もホントのセキになって活きです。 |
図6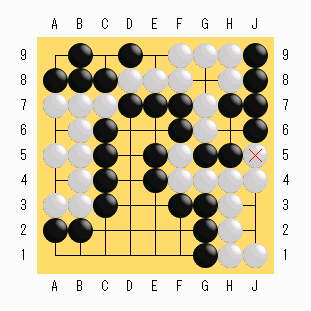 |
と言うことで、この図では白はJ5に手入れが必要になります。 こうしておけば、J3に黒が打っても白はH6に打って黒を取れます。 |
ところで、「日本囲碁規約」第7条に以下の定義があります。 (死活) 相手方の着手により取られない石、又は取られても新たに相手方に取られない石を生じうる石は「活き石」という。活き石以外の石は「死に石」という。 日本囲碁規約にはこのほかにも沢山の条文があり、一部だけを取り出して議論することは問題が有るのを承知で話しを進めます。 上の定義の前半にある、「相手方の着手により取られない石」という表現で、通常の2眼を持った活き石とセキによる活き石の両方を規定しているのだと解釈できます。 ここで問題になるのはセキです。図5でJ5の点は白黒共に打ったほうが損をする点です。だから双方とも打たない。従って「相手方の着手により取られない石」で「活き石」です。 では、図3のJ5はどうか。白黒共に打たない。だったらそこの黒石は「相手方の着手により取られない石」と言えないのか。つまり、「活き石」じゃないのか??? もし、「死に石」だというのなら、J5に手入れが必要なんじゃないのか?! こんな理屈で相手方に迫られたらどうします? おそらく、規約の他の条文を駆使すれば、説明は可能なのだろうとは思いますが・・・。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |