「着手禁止ルール」は必要なのか?
今回もまた昔話をさせて下さい。 |
|
図1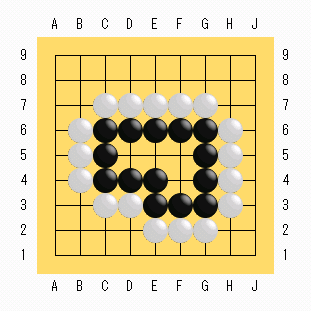 |
大抵の入門講座で、左図のような形の黒は活きだと教えられます。 もちろん私の講座でもそう書いています。 |
図2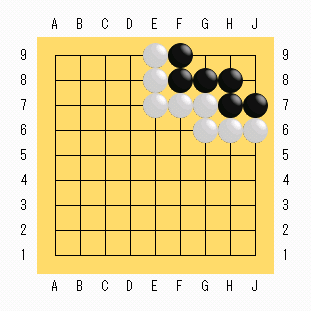 |
でも、大抵の入門講座は、左図のような形については触れていません。 私の講座でも同様です。 どう考えても入門コーナー向きの内容では有りませんものね。 さて、図1が活きだと覚えたばかりの入門者に、「左図の黒は活きか?」と質問すれば、おそらく100%「活き」と答えるのではないかと思います。 私も実戦で痛い目を見るまではそう信じていました。 |
図3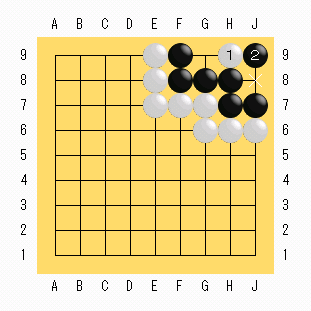 |
白は「1」と打ちます。黒は死なないためには「2」と打つほかはありません。 しかしこの形は、次に白が×(J8)に打ってコウになってしまいます。 上手の白がコウに来た時は大抵やられたと思って間違え有りません。ゴソッと取られて負けました。 私はなんだか狐につままれたようで、隅の不思議を体験したと同時に、この手をいつか使ってやろうと思ったものでした。 |
図4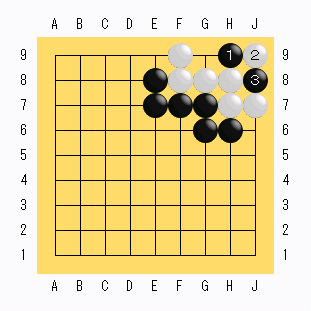 |
で、ある日、そのチャンスが巡ってきました。 左図のようになったとき、「1」と打ち「2」となって「3」を打って、心のなかで「ヤッタ!」と思ったそのとき・・・、 |
図5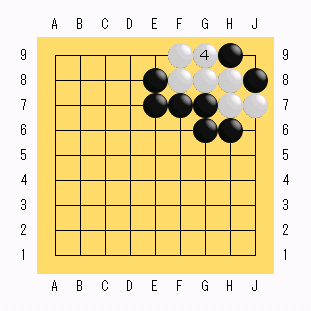 |
白は「4」と打ったのです。 「ゲッ!!!」 私が「押しつぶし」を知った瞬間です。 私はてっきりコウだと思っていましたから、白のどんなコウ立てにもかまわず J9 に繋いで中手にするつもりでした。 しかし図1とは違い、外ダメが2個空いていた為、J9 を「着手禁止」にされてしまったのです。 この経験は「着手禁止」のルールを強く実感した瞬間でもありました。 |
さて、ここまで長い前振りでしたが、本題はこれからです。 確かに上の経験によって「着手禁止」が私の記憶に深く刻み付けられたわけですが、この「押しつぶし」の手筋は「着手禁止ルール」を必ずしも必要としないのではないかと最近考えています。 さらに一歩進んで、「碁にはなぜ着手禁止ルールが必要なのか」について、従来からよく使われている説明とはちょっとちがう考えを持っています。 |
|
図6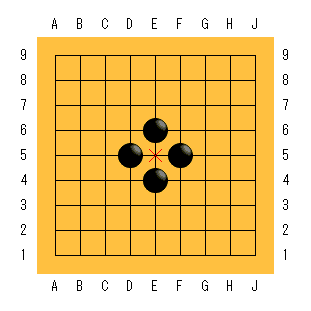 |
現在のルールでは、左図のE5は白にとっての着手禁止点です。 従来の説明では、「そこに白が石を置いても呼吸点を確保できないから、自殺する手は禁止。」と言った理由付けをしています。 私も講座ではそう書いています。まぁ、直感的に分かりやすいですから。 でもこの説明、考えてみると妙な話で、碁では「捨て石」のテクニック(準自殺手)はいたるところに登場します。むしろ、「いかに上手く石を捨てるか」、が腕の善し悪しのバロメーターだったりします。 つまり、「自殺禁止」は「着手禁止」の理由としてはいささか弱いのではないか、と思うわけです。 |
そこで、「自殺手も着手可能」ルールを仮定すると何が起こるか考えてみました。 まず上図の場合ですが、白がE5に打つとその白は盤上に存在できず、即座に黒のハマになります。この石の動きだけを見ると、丼碁(ザル碁)のパスと効果は同じです。でもパスではない。 この手は白にとって1目損です。そして、手番が黒に回ります。確かに「無駄死に」のようにも見えます。 しかし、私の碁なんか「無駄死に」なんてしょっちゅうです。「無駄死に」を禁止されたら碁なんか打てません。 |
|
図7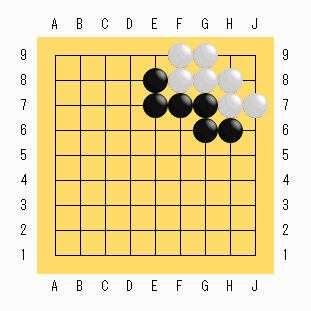 |
次に左図は、図5のJ9に黒が打った直後です。 この形は、白手を抜けません。J9の急所に黒石が来ると死んでしまいます。 しかし、次は白の手番ですからJ9に打って活きることが出来ます。 つまり、着手禁止ルールがなくても「押しつぶし」は成立しています。 ところでこの黒の手、コウ立てとしては有効です。「無駄死に」とは言い切れません。 実際にこの手をコウ立てとして試み、先輩棋士からたしなめられた院生のエピソードが「囲碁が10倍おもしろくなる本」に登場します。 |
いかがでしょうか。着手禁止のルールを自殺禁止だけで説明するのは無理筋だと思いませんか? むしろ、「自殺手も可」とした方が面白いのではないかとさえ思いませんか? 実は私、「着手禁止ルール」の真の必要性は別にあると考えています。 それについては次回のテーマの中で触れさせていただきます。お楽しみに(?)。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |