今まで言って来たことと矛盾するかも?
周りの人間を何人か「碁の虜」にしようと試みてきましたが、どうも確率が悪い。なかなかうまくいかないのです。一応の基礎ルールを理解する段階までは問題ないです。が、そこから先が難しい。 碁はあまりにも自由度が高すぎる為か、ルールを覚えただけでは「何をやっていいのかさっぱり分からない」と言うのが大方の入門者が持つ感想のようです。(特に大人ほどその傾向は強い。) では、碁が打てる為には、ルール以外になにが必要なのでしょう。 それは、例えばポン碁(ポン抜きゲーム)であれば、「石を取る感覚」ではないでしょうか。その感覚が育ってくるまでは、なかなかゲームにならないのです。これは「ポン抜き」を知っている(つまり四つ目取りルールを理解している)段階から一歩ジャンプした段階が必要だと言うことです。 この最初の山というか壁というか、を、越えられるか。そして、それを「面白い」と感じられるかどうか、が問題なのです。 ましてや、「丼碁(ザル碁)」や「純碁」では「石が活きる感覚」が必要になってくるでしょうし、「囲碁」ではそれらの感覚を総合した「地を囲う感覚」が必要になります。 そしてこれら各段階の「感覚」を身につけた上で、さらに極めつけの感覚、「終局の感覚」が備わって初めて囲碁を最初から最後まで打てるようになります。 私はどうもこの感覚の育て方が下手くそらしく、面白さが芽生えるどころか、「碁は難しい」と言う印象の方が先に育ってしまうようです。 さて、またまた長い前振りになってしまいましたが、今回のテーマは「終局」です。 世の中にはいろいろなゲームが有りますが、そのなかで「囲碁」は非常に特殊なゲームだと言ったら言い過ぎでしょうか。 なにが特殊かというと、「囲碁」ほど「終わり方が分かりにくいゲーム」は他に無いように思うのです。(少なくとも私の知る限りは。) 例えばサッカーや野球などに代表される球技類は、基本的には決められた時間(回数)内により多くの得点を取った方が勝ちで、勝敗が決した時点で終了です。 チェスや将棋のようなボードゲームでは、キングとか王将とか明瞭な目標が有って、相手の目標を先に確保した方が勝ちで、勝敗が決した時点が終局です。 他のゲームもだいたい同様で、あらかじめ定められた指標が有って、それを達成した方が勝ち、勝敗が決定した時点でゲームオーバーとなります。 しかし囲碁は違います。勝敗が決定してから終局するのではなく、終局してから勝敗を確認します。 ではどのように終局するかというと、手続きとしては、一方がパスを宣言し、相手方も続いてパスを宣言すると終局です。要するに、対局者の合意、つまり対局者の意志に依存します。 同じような終局手続きのゲームとしてはオセロがありますが、オセロの場合のパスは必然であって対局者の意志が介入する余地が無いため、終局そのものは極めて明瞭です。 また、チェスにも合意の引き分けと言うものは有りますが、対局者が引き分けを確認してから終局するのであって、終局してから引き分けを確認するのではありません。 囲碁は、一方が相手方に終局を打診し、相手が同意して終局となります。そして、終局が合意されてから勝敗確認手続きを行い、これも合意して初めて勝敗が決定します。これが原則です。 では、もし対局者が終局に合意しなかったとしたらどうなるのでしょう。つまりパスをしなかったら何が起こるのでしょうか。 |
|
実験1-1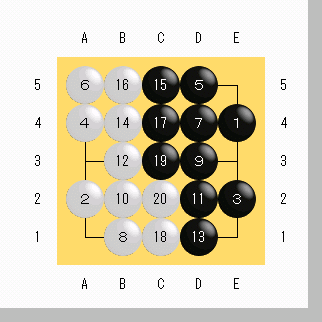 |
この図は何回か出てきました。次は黒番でパス(終局宣言)です。 さて、ここで白が終局を望まなかったとします。 (例えばもし、命でも掛かっているような、どうしても負けられない一局であったとしたら、そして、勝てないまでもせめて戦いが終わらないことを望んだとしたら、白は容易にパスできません。) |
実験1-2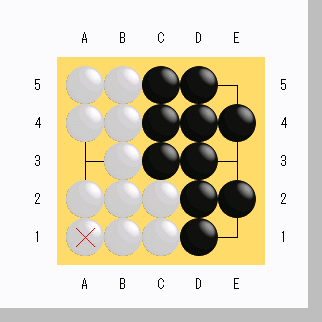 |
白はパスしないとすると、着手可能な点(×)に打つしかありません。 が、黒は続いて再度パスすることになり、今度こそ白は打つ所が無くなりました。 持ち時間の有る碁であれば時間切れになるでしょうし、そうでなければ散々粘った挙げ句、結局終局に同意するしかありません。 |
実験1-3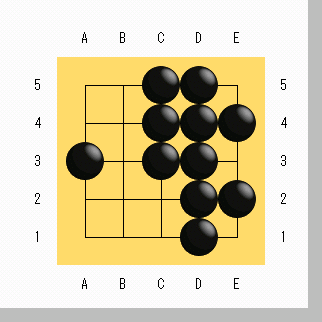 |
黒がウッカリ左図のように取ってしまうと大変です。 白にとって着手可能な空点が沢山出来てしまいました。 いずれ、白の着手可能点は無くなりますが、だからといって白の同意を得られるまではうち続けなければいけません。 |
ここではあえて極端な話をしてみました。しかし、囲碁の終局とはこの実験のような可能性をはらんでいるということです。 この例は意図的に終局を遅らせた話ですが、「終局の感覚」がまだ育っていない入門者の碁では、放っておくとなかなか終われないことがしばしば起こります。そして、置き碁などでは、終局近くになると上手から「そろそろ終わりかな?」などと余計な発言が出たりします。 まぁ、その程度ならまだ良い方で、「ここに1目あるよ」とか、「ここに一手必要だな」などと、中盤の手所では絶対にもらえないであろう「親切なアドバイス」が有ったりします。(私もついついやってしまいます) でも、その「親切なアドバイス」が入門者を混乱させます。 「エッ!、何が・・・?、どうして・・・?」と、頭の中は「?」でイッパイになり、もやもやした気分のまま「碁は難しい・・・」と感じるハメになるのではないでしょうか。 それにしても囲碁の終局は難しい。相当の腕の持ち主でも終局を分かり易く説明するのは難しい(と言うか厄介なもの)と思います。そんな難しい事を入門者に理解しろと要求するのは少々無茶なのではないか、と最近では思っています。 さて、最後にちょっと横道にそれます。 もし前回のテーマである「自殺禁止ルールが無かったとしたら」、つまり自殺手が許されていると仮定するとどうなるでしょう。 上の実験で白はパスせずにE1などの黒の眼に石を打つ事が出来ます。石は直ちに取り除かれ相手のハマになりますが、パスはしていませんから終局に同意したことにはなりません。 白はその意志が有る限り、延々と打ち続ける事が可能になってしまいます。 「着手禁止ルール」の真の意味は、終局を無駄に長引かせる事態を防ぐ為のルールではないか、そう考えているのです。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |