日本囲碁規約考
思いっきり意訳Ⅶ
第十条(勝敗の決定) 1、終局の合意の後、地の中の相手方の死に石はそのまま取り上げ、ハマに加える。 2、ハマをもって相手方の地を埋め、双方の地の目数を比較して、その多い方を勝ちとする。同数の場合は引き分けとし、これを「持碁」という。 3、勝敗に関し、一方が異議を唱えた場合は、双方は対局の再現等により、勝敗を再確認しなければならない。 4、双方が勝敗を確認した後にあっては、いかなることがあっても、この勝敗を変えることはできない。 今回取り上げるこの第十条にはどうツッコミを入れればいいのやら、正直困りました。 そこで、少々昔話をさせていただいてお茶を濁そうかとおもいます。 私が初めて碁を教えられたのは、たしか小学校4年か5年の頃、家族で近所の温泉に一泊したときだったと記憶しています。 そのころの旅館には床の間に将棋盤や碁盤が置いてあるのが普通で、そのかわりテレビなど今では当たり前になっている設備はありませんでした。 風呂にも入り食事も終わって、寝るまでの時間を持て余した親父が私を碁盤の前に座らせて暇つぶししようとしたのが、私が碁にハマるきっかけになりました。 その時親父が私に教えたのは、「とにかく大きく囲め。大きく囲った方が勝ち。」でした。 |
|
図1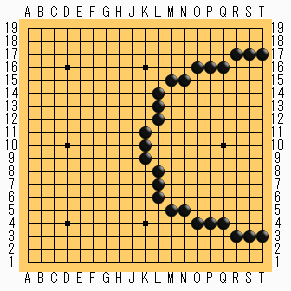 |
「大きく囲め」といわれて、私の頭に浮かんだのがほぼ左図のような姿です。 頭のなかの碁盤には黒石しかありません。 右側を半円形で囲ったつもりです。 この図をめざして第一着を打ちました。 |
図2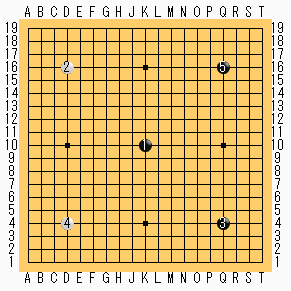 |
白の手ははっきり覚えていませんが、5手までは大体こんなふうだったとおもいます。 初手天元を見た親父が「おっ!」とかなんとか言ったような言わなかったような。 このあと私は図1を目指して数手打ちましたが、目論みは見事に崩れ去ることになります。 結局どんな形になったかは忘却の彼方ですが、囲碁というゲームにおける「囲む」ということがどういうことなのか、サッパリわからなかった記憶だけは残っています。 |
この日の事はこれ以上思い出せません。 おそらくこの生まれて初めての一局は中断せざるを得なかったでしょう。なにしろ打つ場所を選ぶ基準が全然わからない私が打ち続けられるはずがありませんから。 それにしても親父の教え方も相当なものです。四つ目殺しとか、そう言ったことを一切教えずにいきなり「囲め」ですからねえ。しかも19路で置き石無しです。私の提案している「丼碁(ザル碁)」とは全く対照的な教え方です。 にもかかわらず、私は碁にハマリました。 その後たびたび親父から碁を教わることになりましたが、井目風鈴中四目に鉄柱とさらに中央に4子を足してもなかなか碁らしくなりません。 それでも何局かやっているうちに、親父の誘導のままになんとか地らしきものが作れるようになり、ダメ詰めしてやっと整地する段取りまでたどり着く日がきました。 そこで登場するのが今回のテーマである第十条の 1.と 2.に書かれている事柄です。 親父は、「この黒は死んでいるから。」と言いつつ盤からどんどんはがします。しかもその黒石を私の地の中に置いていくではありませんか。 私はあっけにとられたというか、狐に摘まれたというか、どうしてそういうことになるのかさっぱり理解できませんでした。 そもそも最初の日に教えてもらった あの「大きく囲め」 はいったい何だったんだろう、と。 数あるゲームのなかでも、ルールブックのこれほどお終いに近いところに「勝敗が如何に決するか」の記述があるのは日本囲碁規約くらいのものではないでしょうか。 逆に言えば、日本囲碁規約では勝敗決定方法を記述するために周到な下準備が必要だったということになります。 このことは、入門者にとって囲碁がわかりにくいと言わしめる大きな要素となっているのは間違いないだろうとおもいます。 じゃぁ、どうすれば分かり易くなるんだ、と問われるとなかなか決め手は無いのですけど、手前味噌になりますが「丼碁(ザル碁)」はその有力な解決法の一つではないかと考えます。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |