日本囲碁規約考
思いっきり意訳Ⅵ
第九条(終局) 1、一方が着手を放棄し、次いで相手方も放棄した時点で「対局の停止」となる。 2、対局の停止後、双方が石の死活及び地を確認し、合意することにより対局は終了する。これを「終局」という。 3、対局の停止後、一方が対局の再開を要請した場合は、相手方は先着する権利を有し、これに応じなければならない。 さて、いよいよ第9条です。第9条は長い戦いを終わらせるための手続きが決められています。 チェスや将棋は、どちらかの大将の首が飛んだとたんに勝負が決します。その為ゲームの終了は非常に分かり易く、手続きもへったくれもありません。しかし碁には終了を客観的に判断するための明確なイベントが有るわけではありません。碁は双方が出来るだけ多くの領地を争奪し、その多い方が勝ちになるのですが、「もうどちらの領地も増やせないし減らすこともできない」と対局者が共に判断したとき戦いが終わることになります。 しかしそれだけでは勝敗が決したことになりません。勝敗を決する為には双方が確保した領地の広さを比較する必要があります。そのためには領地の境界が明確になっていなければ判定ができません。 ところがこの境界線について、両者の意見が一致しないという事態が起きることがあります。 そのような事態に対応するための約束事をこの第9条は規定しています。 |
|
図1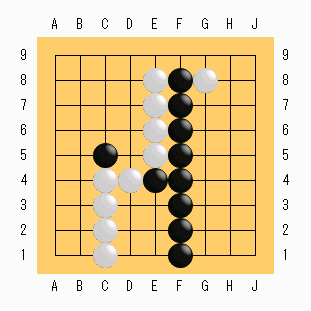 |
左図のような局面になったとします。 コミは無く、ハマも無しで現在黒番です。 |
図2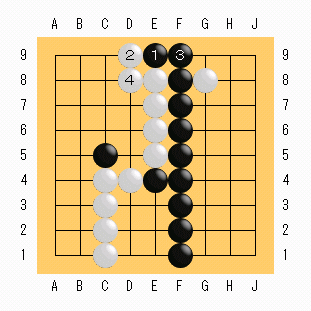 |
図1の左上方面は白にとって極めて味の悪い形ですが、黒はそこに手段を求めることはせず、単純に上辺のハネツギを決めました。 左図で黒は勝てると目算しているが故の判断でした。 黒は「終わりですね」と言い、白は「そうですね」と応えました。 この「終わりですね」は「私にはこれ以上儲ける着点がありません、どうぞお打ち下さい」という意味で、第9条-1で言うところの「着手放棄」に相当します。 そして、「そうですね」も同様に「着手放棄」です。 従って、両者の着手放棄が連続したのでこの時点をもって「対局の停止」となります。 |
図3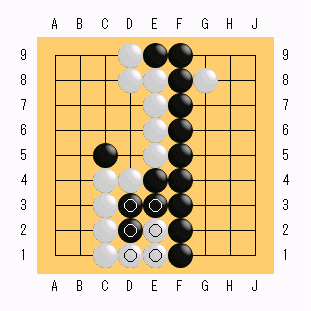 |
ここから第9条-2に書かれている「石の死活と地の確認」を行うことになります。 左図の丸印の石はいわゆるダメ詰めです。前回の第8条によりダメが空いていると地が完成しませんから、このダメ詰めこそが「地の確認」にあたります。また、C5の黒とG8の白が死に石で、その他の石は活き石であることをやはり第7条により確認します。 死活と地について両者の意見が一致した時点で終局となります。 |
では、一旦ここまでのところをまとめておきましょう。 第9条-1で言うところの「対局の停止」とは、「停戦協定の締結」だと考えています。戦闘のこれ以上の継続が無益であると、両対局者の判断が一致した時点で一時停戦すると考えると分かり易いのではないでしょうか。 ただし、これはあくまでも一時停戦であって終戦ではないのです。なぜなら、両者の確保した領土の認識が必ずしも一致しているとは限らないからです。 第9条-2は両対局者が確保した領土をお互いに認め合う、いわば「終戦処理」だと考えます。境界が不明瞭な場所にしっかり杭を打つ、これが終戦処理です。 両者からの異議がなく境界線が確定した時点で「終局」、つまり終戦です。 しかしながら、対局者の一方が境界線に欠陥があると主張したのに対し、もう一方は十分立派な境界線が敷けていると主張し、双方の意見が一致しない場合があります。 そのような事態に対応するための条文が第9条-3です。 |
|
図4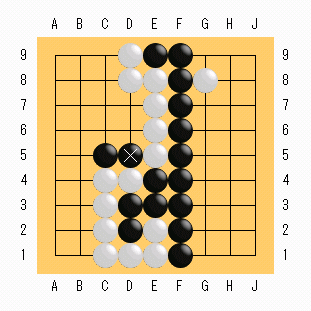 |
黒は「終わりですね」と言ったとき、ダメが詰まると左図の×に切る手が生ずるのではないかと考えていたとします。 (実際にその手が成立するかどうかは関係有りません。黒がその手が成立すると信じている点が重要です。) つまり、「白は終局までに×の点にツギ、境界の欠陥を繕う必要がある」と黒は考えていたとします。 一方白は黒から×に切ってきても問題はないと考えているとします。 |
第9条-3はこのような意見の対立が起きたときの解決手順を決めています。 手入れが必要であるはずなのに相手がそれをしない、そんなとき戦闘再開を宣言します。それが「対局再開の要請」です。 再開要請を受けた側はその要請を拒絶できません。ただし、拒絶できない替わりに再開の際先着する権利を与えられます。とはいっても、そもそも自陣に欠陥は無いと考えていれば、当然着手放棄を選択する事も出来るわけです。 以上が第9条の一般的な解釈だと思います。 さて、この第9条(終局)については、その「曖昧さ」をテーマにいろいろな議論が聴かれます。ここからは、この「曖昧さ」について少し考えてみたいとおもいます。 ※その1.着手放棄の確認について。 図2で黒が「終わりですね」と呟いたとき、白が何も反応しなかったとしたらどうでしょう。 黒は着手放棄したつもりで、白の応えを待っています。白は黒が何か独り言を呟いたのは聞こえたが、黒の手番なので打つのを待っています。 もしこんな場面になったら、黒はハッキリ「お打ち下さい」とか「私はパスです」とか発言して白の着手を促すべきでしょう。 また、白としても「終わりですね」が聞こえたときは「パスですか?」と確認するのが良いと考えます。 なぜなら、黒の「終わり○×△※」と言う呟きを、白が着手放棄だと勝手に解釈し、確認することなしに下図のように打ったとしましょう。 |
|
図5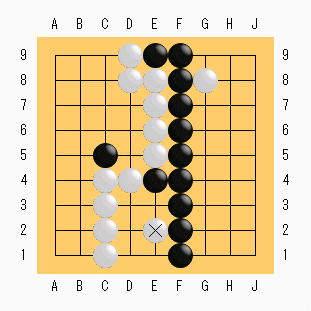 |
この×の白は、黒の着手放棄が無ければ、形の上では2手打ちです。 もしこの瞬間に黒が着手放棄していないと主張すれば、白は反則負けになってしまう危険性すらあるのです。 |
しかし実際に行われている対局で、このように明確に着手放棄する姿を見たことはありません。プロのテレビ対局などでも、目を合わせ軽く会釈でも交わせば良い方で、それすら無くいつのまにか駄目詰めが始まり記録係が終局を宣言するのが普通になっています。 これは、盤面を観ていれば「誰でも終局だと判断できる」という考えが前提に有るからだと思います。しかし、私程度の棋力では解説者の説明がなければまだヨセが残っているように見えることもよくあります。 我々素人が楽しみで打つ碁ではもっと訳が分からない終わり方をする場合があります。「終わりですね」なんて発言も何も無く、駄目詰めしながら整地もしないまま「検討」が始まっちゃったりするなんてことも珍しくありません。 まぁもっとも我々素人の碁は必ずしも「日本囲碁規約」で打っているわけではないのでそれでも良いのかもしれませんが、やはりプロの碁は明確に規約に則って手続きを踏んで欲しいと言う気がします。 そして我々素人も、出来るだけ規約を意識して打つことを心掛けるのが望ましいと考えます。 ※その2.価値のある手は万人に共通か。 図2で、黒の「終わりですね」について、「着手放棄」であることを確認した上で白はそれに同意せず、図5のように打ったとしましょう。 図5を見て下さい。もし白がもう一手続けて打てばそこに2目の地が出来る形です。 確かに次に黒が正しく応じればここには1目もできません。 しかしそれにしても、2手続けて打てば得をするこの様な形での×の一着ははたして単なるダメ詰めと言って良いのでしょうか。 私にはこれも有効な一着であるようにも思えるのです。例えば、 |
|
図6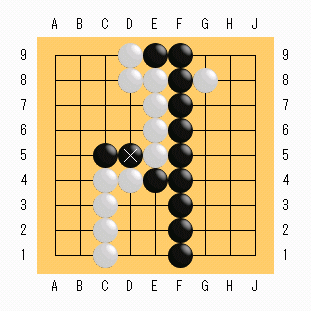 |
図2の後、左図の様に黒が切りを入れたとしましょう。 もし仮にこの後の変化でコウが発生したとすると、下辺への一着は立派なコウダテとしての価値を持つことになると思うのです。 そのコウダテを消す意味であれば、下辺のダメ詰めもまた価値有る一手なのではないでしょうか。 もし白がそのような心配をした結果、黒の一時停戦の申し出を受けずに下辺に打つダメ詰めは立派に意味のある手だと思えるのです。 この場合も実際にコウが発生するかどうかは関係ありません。白がそのような事態を心配した結果の判断だと言うことです。 |
一手に価値があるかどうかの判断は、対局者の棋力やその人が普段打っているルールによって変わってきます。たまたまその対局が「日本囲碁規約」で行われていたとしても、対局者の頭の中ではおそらく普段一番なじみの深い発想で判断しているだろうと想像できます。 一手の価値の判断は、本来あくまでも対局者個人のものであって、他人にとやかく言われる筋の物では無いはずです。しかしながらなぜか終局時点ではあたかも共通認識であるかのようにみんなが振る舞っている。わたしには不思議に思えます。 ※その3.人は皆善人か。 ここまでこの碁はコミ無しで考えてきましたが、実はコミが有ったとしましょう。 図2の後、黒も白も着手放棄をし、対局の停止となり、死活と地の確認をしている途中で黒は計算違いに気が付きました。 そこで、黒は対局の再開を要請しました。もし白が用心して一着手を入れてくれれば1目得です。また、もし白がパスで応じてくれれば、駄目元で図6の切りを実行しようというわけです。 それにしても、この対局再開の要請は許されて良いのでしょうか。 「このような恥ずかしい行為をする碁打ちはいない」、という前提で日本囲碁規約は作られているのでしょうが、対局の要請をした人が真剣に有効な手順を発見したと信じているのか、それとも駄目元で手を試してみようとしているだけなのか、などという事は他人にはおよそ伺いしれないことであるからには、規約上この要請を制限しようがないように思えます。 しかし、なんだか「待った」をルールで認めているようで釈然としないというのが正直なところです。 このように「終局の曖昧さ」といっても色々な側面があります。 ※「その1」で挙げたような事柄は規約の遵守で解決可能な内容です。これはもう規約を運用する当事者の意識改革こそが問題解決の唯一の方法でしょう。 ※「その3」の事柄は規約に手を加えることで解決できるかもしれません。しかし、このような「人の心の揺らぎ」に根ざす問題はどのような形で現れるか想像もできません。従って結局は「良識と相互信頼」に頼らざるを得ないでしょうし、トラブルとなれば第三者の裁定に委ねるしかないでしょう。 ※「その2」の事柄、実はこれが一番やっかいです。 碁というゲームには、元々その根本の所に実は「曖昧さ」が有ると私は考えています。つまり、石の死活について客観的で明確な定義が無いということです。 このコラムでも「死活」のところで述べましたが、対局者が活きと合意した石が活き石なのです。第三者がなんと言おうと、対局者両者が活きだと言えば活きなのです。この活き石の定義の仕方は、そうするしかないのでこのような定義になっているのです。 理想としては、論理的(数理的と言っても良いかもしれない)に死活を定義したいのです。しかし現在の所、碁が発明されてから四千年にもなろうとしているにもかかわらず、客観的に証明可能な石の死活の定義は発明されていません。このことが碁の「曖昧さ」の根本に有ると考えられます。 この「曖昧さ」はなにも日本ルールに限られたことではなく、他のルールでも同様に有る問題です。しかし、石の多少で勝敗を決するルールでは、もし対局者の間で死活に関する解釈の相違が起こったとしても、それを実戦において実力で解決する手段があります。 ところが、地を争う日本ルールの場合、実戦的に解決しようとすると双方の地が影響を受けてしまうことになり、「実戦解決」という手段がとれません。 そこで発明されたのが「対局の停止」であり「死活確認」であり「対局の再開」であると考えられます。 これらの発明は、原則として、対局の当事者が当事者間だけで問題を解決できるようにするための工夫であって、実戦解決と言う手段を持たない「地を争うルール」において第三者の介入なしに決着を付けることを可能にするための規定であると考えています。 「曖昧な石の死活」に根拠を求める「地」は根本的に曖昧なのは避けられません。したがって、その「曖昧な地」を争う日本ルールは曖昧にならざるを得ず、厳密な石の死活が発明されない限り「日本囲碁規約」も完全に厳密には成り得ないと私は考えています。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |