日本囲碁規約考
思いっきり意訳Ⅴ
第八条(地) 一方のみの活き石で囲んだ空点を「目」といい、目以外の空点を「駄目」という。駄目を有する活き石を「セキ石」といい、セキ石以外の活き石の目を「地」という。地の一点を「一目」という。 この第8条は、短い文でありながらなかなかの曲者ではないかと私は思っているのです。 まずは下図を見て下さい。この図で何処が「地」に該当するのか、第8条に照らして考えてみていただきたいのです。 碁の常識に十分なじんだベテランの碁打ちにとっては特に難しい事はない問題でしょう。しかし、入門者やそれに近い初心者にとってはどうでしょうか。 |
|
図1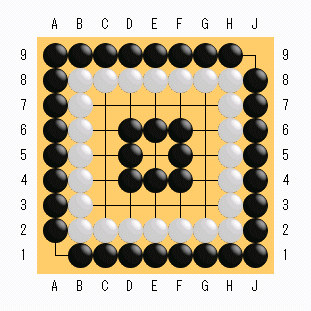 |
「地」を考える為には石の死活が分かっていないといけませんが、初心者にとっては、この図の死活からして難しいかもしれません。 死活について結論を言ってしまえば、白石は全滅で黒石は全て活きです。 では、死活が分かったところで、「地」はどうなっているのでしょう。 第8条に依ると、「地」は「目」でなければいけません。そして、「目」は一方のみの活き石に囲まれた「空点」である必要があります。 左図でこの条件を満たす「空点」とはいったい何処のことでしょう。 |
図2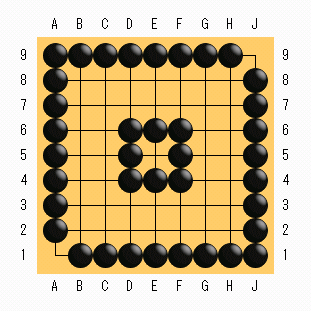 |
碁の常識をいまだ持ち合わせていない人にとって、第8条に沿って図1の「地」を考えることはまず無理ではないでしょうか。 実は、碁の常識では図2の様に、死んでいる白石を盤上から取り除いた状態を想定して「地」を考えているのです。 この図であれば第8条に沿った「目」を、そして「地」を考えることは容易だと思います。 この図では、盤面の空点全てが黒地と言うことになります。 |
さて、次に下図の「地」を考えてみて下さい。 |
|
図3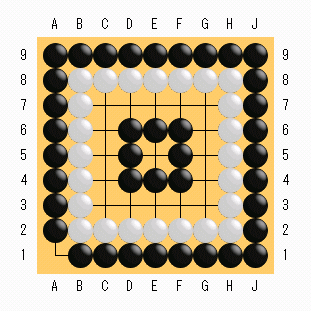 |
左図と図1とは J9 の1点だけが異なっています。 その為、石の死活が逆転していて、黒は全滅、白は全て活きです。 この問題も前問同様死に石を盤面から取り除いたと想定して「地」を考えます。 それが次図です。 |
図4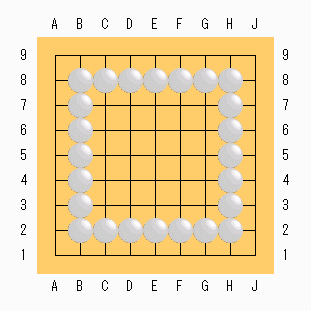 |
左図に第8条を適用してみて下さい。 ここで問題になるのは、日常会話で使う言葉と碁の世界で使っている言葉の概念が少々異なっているという点です。 左図で、白石に「囲まれている」空点とはどこの事でしょうか。 碁の常識に馴染みの薄い入門者にとって、白石の「外側」つまり辺とか隅とかの空点が白石に「囲まれている」と認識するのは直ぐには難しいのではないでしょうか。 しかし、碁の常識ではこの図の全ての空点は白石に囲まれており、白地と言うことになります。 |
次にもう一つ下図を見て下さい。 |
|
図5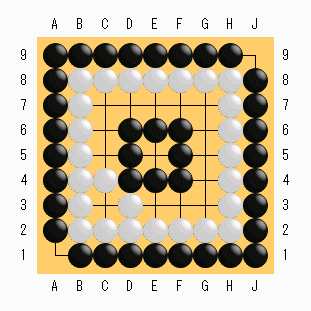 |
これは図1の白石に眼を一つ付け加えた形です。 この図の石は白も黒も全て活きています。 ただし、第8条の規定によって、中央の黒石とそれを囲む白石は「駄目」を有するので「セキ石」です。 ということは、E5 や C3 の空点は「目」ではあるが「地」ではありません。 「地」は A1 と J9 の空点だけが2目の黒地ということになります。 |
図6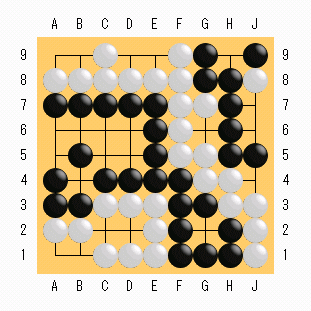 |
さて、ここでベテラン碁打ち向け注意事項を一つ取り上げておきます。 左図はこのシリーズの始めに紹介したものです。もしこの状態で終局したとしましょう。 ここで注意すべきは G6 と J4 の二つの「駄目」が有る点です。 ということはその駄目を持っている上辺から右下に渡る一連の白石と右上の黒石は「セキ石」だということです。 しかしこれらの石がセキ石だということを、ベテラン碁打ちはすんなり認めてくれるでしょうか。 またセキ石の「目」は「地」ではない事も注意する必要があります。つまり上辺にも右上にも「地」はありません。 |
この第8条には、入門者にとっても、またベテランにとっても、それぞれの常識とは若干異なる(というか、拡張された)概念が使われているところが重要です。この拡張された概念を受け入れることなしに日本囲碁規約を受け入れることはできません。 日本囲碁規約に関する様々な論評のなかで、これらの拡張された概念を受け入れずに、あるいは認識を持たずに考察されたと思われるふしのあるものが見られるのは残念です。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |