作戦
こう打てばポン碁に勝てる
相手の石を取るための方針を考えます。
図3-1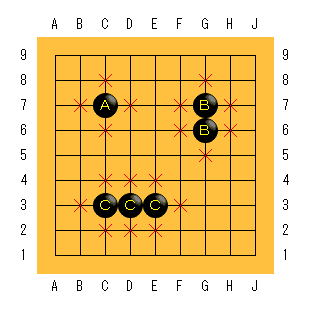 |
まず、運命共同体は大きいほど取るのに手間が掛かることを覚えて下さい。 例えば、Aの石は呼吸点が4個ですから、白が4手打てば取られます。同様にBは6手、Cは8手で取られます。石が一つ増える毎に手数が2手増えています。 呼吸点を奪う立場では、一手で一個の呼吸点しか奪えないのに対し、運命共同体に石を追加する立場では、一手で最大2個の呼吸点を増やすことが出来ます。 このことから、碁は一手ずつ交互に打つゲームですので、攻める(呼吸点を減らす)より守る(呼吸点を増やす)方が有利なことがわかります。 |
図3-2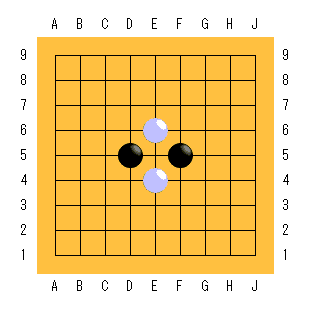 |
右の図は、4個の呼吸点を持った黒石2個と白石2個がにらみ合っている状態です。 ではこの状態で、いま黒が打つ番だとして、どこに打つのが良いと思いますか? |
図3-3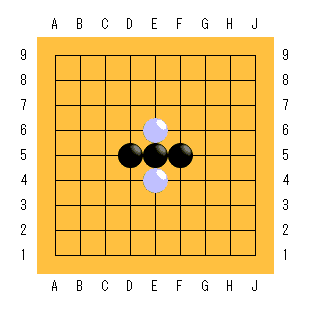 |
そうです。このように真ん中に打つのがいい手です。 黒は呼吸点を6個持つ運命共同体に変身したのに対し、白は2個の石の呼吸点を共に3個に減らしています。 つまり、黒は取られ難くなり、白は取られ易くなっています。 このような、自分の呼吸点が増え、相手の呼吸点を減らすような手は非常に有効です。 言い換えると、自分はつながり、相手を分断するような手が戦いを有利にします。 |
図3-4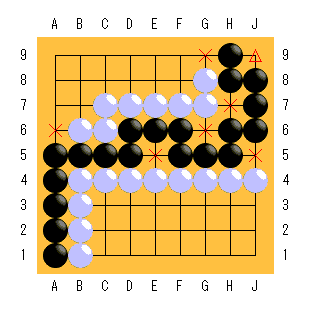 |
ただし、つながった大きな運命共同体であれば良いのかと言うと、そうとは限りません。 下手に打つと右図のようになってしまうかもしれません。 黒は呼吸点を7個持っていますが、×の点は白が打てる場所ですし、×が全部埋まった後であれば、△の点も白から入られてしまいます。 この巨大な黒は結局全部取られてしまう運命です。 大きければ戦いには有利ですが、絶対安全と言うわけではありません。 |
図3-5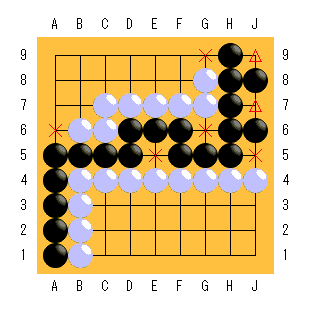 |
この図は上の図と比べて黒石1個の位置が違うだけですが、白から奪えない△の2点がありますので、全体の黒は安全です。 しかし、ポン碁に勝てるかと言うと、はなはだ怪しい状態です。 なぜなら、今から白石を取りに行ったとしても、取りに行った黒が逆に取られる心配の方が大きいように見えるからです。 |
図3-6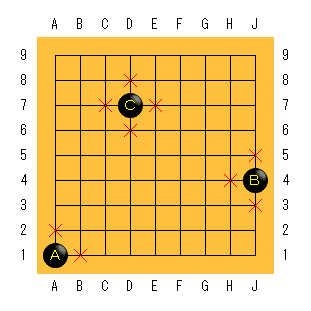 |
この3個の黒、どれが一番強そうで、どれが弱そうですか? Aは呼吸点が2個しかなく、Bは3個、Cは4個です。 呼吸点が沢山有る方が元気な事は明らかです。 その目で上の図を見て下さい。 黒は端っこの石がやたら多いですね。 碁は元気な手を沢山打った方が有利になります。 |
図3-7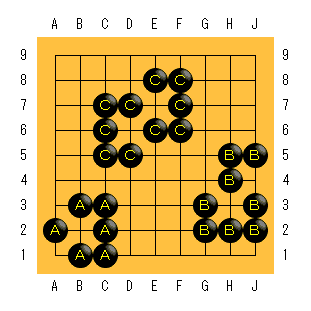 |
反面、絶対に取られることのない石、つまり生きた石になるのには、端っこのほうが便利です。 Aは6個の石で生き形ちですが、Bは8個、Cは10個です。 |
図3-8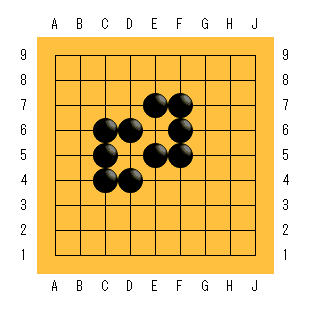 |
盤の中央で生きる為の最小の形がこれです。 |
図3-9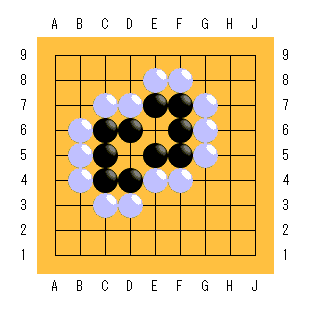 |
これは、最小の生き形ちを包囲した図です。 |
図3-10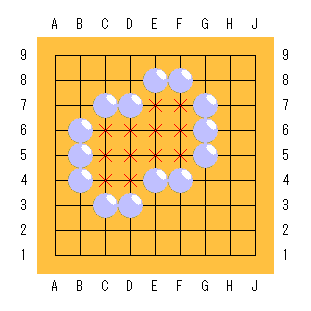 |
囲んだ白石だけに注目してみましょう。 見方を変えて言えば、これだけの空間(×の点の集まり)が無いとその中で黒は生きられないと言うことです。 |
図3-11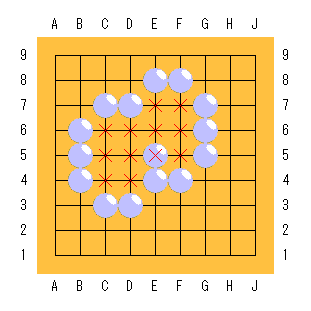 |
もし黒が10手連続で打つことができれば包囲網の中で生きられますが、碁は交互に打つゲームですから、どこかで一手邪魔が入れば生きられない。 ×の点のどれか一つに白が打てば、最小の生きを確保するスペースが無くなってしまいます。 つまり入っていった黒石は取られてしまいます。 |
図3-12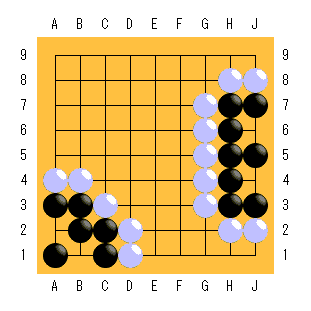 |
端っこでも同じ事がいえますが、どうしても取られたくない状況では、端っこのほうが広い空間を必要としないので有利です。 |
図3-13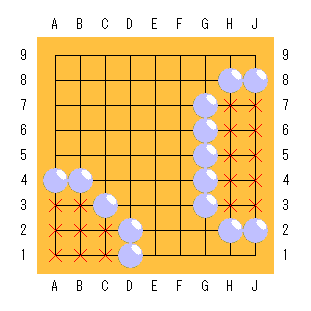 |
生きに必要な最小の空間を作らないようにすれば、その中で相手の石は生きられません。 あるいは、相手の石を最小の空間に閉じこめてしまえば、タイミングを見計らって生きを邪魔できます。 つまり、相手の石を取れます。 |
| 以上より、戦いの方針をまとめます。 1.自分の石をつなぎ、相手の石を分断する手を考える。 2.元気な手を相手より沢山打つように心掛ける。 3.相手の石を最小の空間に閉じこめる手を考える。 4.自分の石が最小の空間に閉じこめられないような手を考える。 この4項目を心掛ければポン碁の勝率はぐんと上がります。 |
| 次のテーマ | いつまで続く? |