逆転の発想
丼碁(ザル碁)と純碁を考える
碁にもいろいろありますが、本質は同じです。
| 囲碁の入門用として、王銘琬九段が提案されている「純碁」というものがあります。 この純碁は、基本的なルールは囲碁と同じで、ゲームの目的、つまり勝敗を判定する方法だけが囲碁と異なります。(詳細は純碁 10分で覚えられる囲碁を参照してください。) 実は丼碁(ザル碁)も同様で、勝敗の判定方法以外のルールは共通です。 丼碁(ザル碁)と純碁のルールの違いを確認しておきます。 (囲碁のルールとの比較は次のコーナーで扱います。) 共通ルール。 ・碁盤に引かれた線の交点に、黒白交互に石を置く。 ・一度置いた石は動かせない。 ・相手の石を囲めば取れる。 ・コウはすぐに取り返せない。 丼碁(ザル碁)の勝敗判定ルール。 ・石を沢山取った方が勝ち。 純碁の勝敗判定ルール。 ・石を沢山置いた方が勝ち。 要するに、双方の手元にある石の数を比べるか、盤上にある双方の石の数を比べるかの違いです。 では具体的に見ていきましょう。 話を簡単にするために、5路盤で考えます。 |
図4-5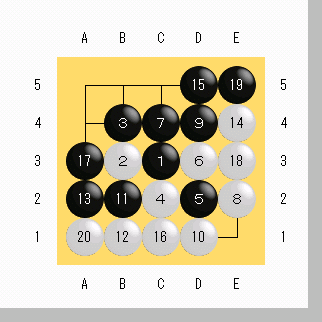 |
5路盤の実戦例です。 いま、白が20を打ったところです。 |
図4-6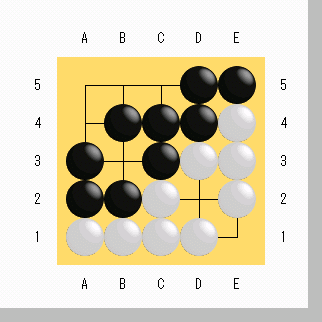 |
次は黒番で、左上方面の空点に打つ余地があります。 しかし白は、左上の黒の勢力圏に打てないことはないのですが、打っただけ取られてしまうことは明らかで、実質もう次に打つ所がありません。 |
図4-7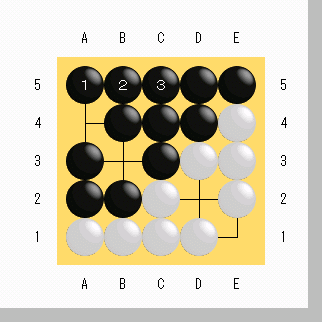 |
ではまず、丼碁(ザル碁)ルールで考えます。 黒が左図のように3手打つ間、白は打つ所がありませんから3回パスをし、ペナルティとして計3個の白石を黒さんに渡します。 で、とうとう黒も打つところが無くなり、白さんに黒石を1個渡してパスです。 白パスと黒パスが連続したので終局です。 |
さて、勝敗はどうなっているでしょうか。 黒さんは、B2に有った白石1個を17手目で取っています。また上図の黒1~3までの間に白がパスのペナルティとして渡した3個の白石を持っています。黒さんは白石を合計4個取りました。 白さんは、D2に有った黒石1個を10手目で取っています。そして、黒が最後にパスした時に、ペナルティとして渡した1個の黒石を持っています。白さんは黒石を合計2個取りました。 結局、黒さんが2個多く石を取って勝ちです。 では次に純碁ではどうでしょうか。 |
|
図4-8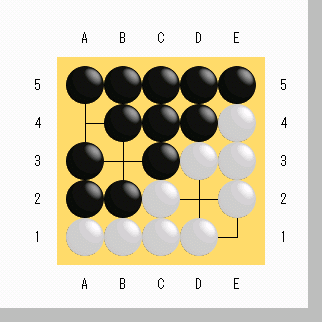 |
純碁では、取った石は勝敗の判定に関係ないので、パスによるペナルティは有りません。 (それどころか、途中で取った石も相手に返してしまいます。) 図4-7の手続きを盤面だけ見ていれば、純碁も丼碁(ザル碁)も、なんら変わりありません。 最後の姿は同じですが、純碁の勝敗判定は盤面の石数の差によります。 盤面の黒石は12個、白石は9個です。 結局、黒さんが3個多く石を置いて勝ちです。 |
このゲームで使われた石の運命にのみ注目した表を作ると下のようになります。
| 「○」は盤上に残った石を、 「×」は取られた石を、 「◎」は勝敗に影響する着点がなくなった時点以降に、自陣を埋めた石を、 「P」はパスを表します。 |
||||||||||||||
| 手番 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 黒 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | P |
| 白 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P | P | P | |
| 手番 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| 要するに、黒白それぞれについて、丼碁(ザル碁)では「×」と「P」の合計(手元の石数)を、純碁では「○」と「◎」の合計(盤上の石数)を数え、その差で勝敗を判定していることになります。 一見違うものを数えているようですが、盤上の石と手元の石の合計は総手数(パスも手数に加える)ですから、どちらを数えても同様な結果が得られるのでした。 数式で確認しておきます。(数式の苦手な人は無視してください。) [丼碁(ザル碁)の計算] 黒の得点 = 白×石 + 白P石 白の得点 = 黒×石 + 黒P石 得点差 = 白×石 + 白P石 - 黒×石 - 黒P石 [純碁の計算] 黒の得点 = 黒○石 + 黒◎石 白の得点 = 白○石 得点差 = 黒○石 + 黒◎石 - 白○石 ところで、上の表では 黒の手数 = 黒○石 + 黒×石 + 黒◎石 + 黒P石 白の手数 = 白○石 + 白×石 + 白P石 ですが、黒と白は交互に着手していますから、最後の「黒P石=1個」を考慮すると 黒の手数 = 白の手数 + 1 なので、 黒○石 + 黒×石 + 黒◎石 + 黒P石 = 白○石 + 白×石 + 白P石 + 1 となり、左辺と右辺の項目を入れ替えて、 黒○石 + 黒◎石 - 白○石 = 白×石 + 白P石 - 黒×石 -黒P石 + 1 です。これは、 純碁の得点差 = 丼碁(ザル碁)の得点差 + 1 となります。 この例では得点差に1ポイント違いがでましたが、これはたまたま最後のパスが黒の番になったからで、もし白が最後のパスをするような場合は、純碁も丼碁(ザル碁)も全く同じ結果になります。 数式が苦手な人は結論だけ覚えておいて下さい。 純碁の計算でも丼碁(ザル碁)の計算でも本質的には同じということです。 丼碁(ザル碁)では「沢山取れるように打つ」作戦を立て、純碁では「沢山置けるように打つ」作戦を立てて戦うわけですが、「沢山取る」と「沢山置く」は表現が違うだけで同じテーマだと言えます。 丼碁(ザル碁)は石を多く取ることが目的であるために、ただひたすら相手の石を追いかけ回す作戦になりがちです。しかし、それだけではなかなかうまく行かなくなってきます。 そこで視点を少し変えて、自分の石だけを置くことができる自分専用の領域を沢山確保する、つまり、「広い自陣を持つことを目指す純碁的感覚」を発想に加えることが出来れば、作戦の幅がグンと広がることでしょう。 |
| 次のテーマ | 効率の追求 |