細かいことが気になって
入門講座の最後の方で、丼碁(ザル碁)と他の碁の得点計算について比較しているコーナーがあり、そこでは、「細かいことはさておき、どの碁も本質は同じだ」と書いてあります。 確かに、ルールの違いによるスコア計算の多少の差違よってゲームの面白さが損なわれるものではありません。しかし、碁も勝負事である以上、この「多少の食い違い」が大きな問題になる場合がありえます。 そこでこのコーナーでは、ルールの差が勝敗判定にどう影響するのかを考えます。 |
|
例1-1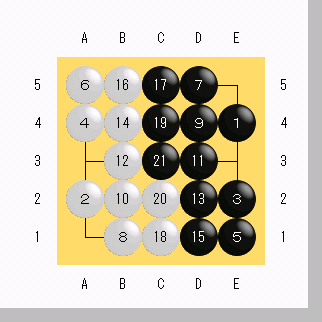 |
話を簡単にするため、5路盤を使います。また、テーマの本質を見失わないため、非現実的だが分かり易い左の手順で考えます。 黒21で打つ所が無くなりました。 囲碁も純碁も丼碁(ザル碁)も、黒21の後白パス、黒パスで終了します。 石の取り合いによるハマは有りませんが、丼碁(ザル碁)だけは、パスにともなう石の交換によるハマを、黒白ともに1個ずつ持っています。 |
囲碁は地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒2目、白2目で、引き分け(持碁)。 純碁は盤上の石を数えます。たとえハマがあっても純碁では関係ありません。 黒11個、白10個で、黒1個勝ち。 丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、最後のパスにともなうものだけです。 黒が白石1個、白が黒石1個で、引き分け(持碁)。 以上より、このケースでは囲碁と丼碁(ザル碁)が同じ判定で、純碁の判定が異なります。 |
|
例2-1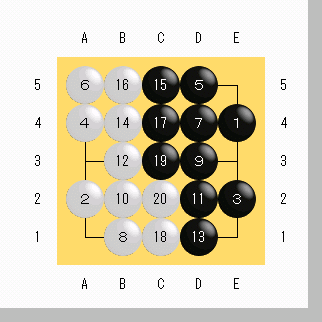 |
次にこの手順で考えます。 囲碁では白20で終了ですが、純碁と丼碁(ザル碁)は下図のように黒が自陣に打ちます。(下図×印の石) |
例2-2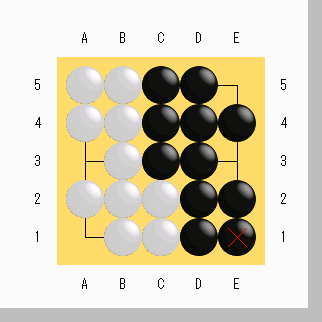 |
純碁はこれでお終い。 丼碁(ザル碁)では、次に白がパス(黒に白石を渡す)。続いて黒パス(白に黒石を渡す)で終了です。 |
囲碁は(例2-1)の地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒3目、白2目で、黒1目勝ち。 純碁は(例2-2)の盤上の石を数えます。 黒11個、白10個で、黒1個勝ち。 丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、最後のパスにともなうものだけです。 黒が白石1個、白が黒石1個で、引き分け(持碁)。 以上より、このケースでは囲碁と純碁が同じ判定で、丼碁(ザル碁)の判定が異なります。 いかがでしょうか。微妙な差です。この差はどこから出てくるのでしょう。 例1-1図と例2-2図を見比べてみて下さい。どちらも同じ姿ですね。 純碁と丼碁(ザル碁)では、手順は違いますが最後の姿が同じため、例1と例2で同じ結果になります。 しかし、囲碁の場合例1と例2では最後の姿が違います。当然結果も違います。その違いは手順の違いから来ています。 この事は、純碁や丼碁(ザル碁)においては勝負に影響しないような些細な手順前後も、囲碁では微妙に影響する可能性があることを示しています。 |
|
例3-1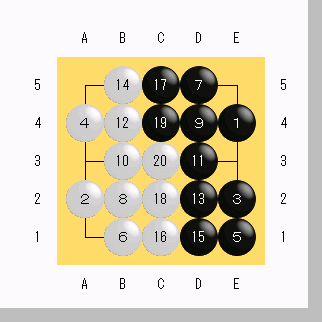 |
では最後にもう一つ。 囲碁では白20で終了ですが、純碁と丼碁(ザル碁)は続きが有ります。 |
例3-2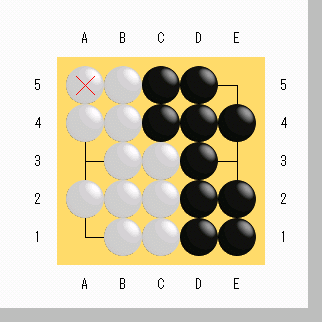 |
黒番ですが打つところが無いのでパス(白に黒石を渡す)です。 次に白が×に打ちます。 純碁はこれでお終い。 丼碁(ザル碁)では、次に黒パス(白に黒石を渡す)。続いて白がパス(黒に白石を渡す)で終了です。 |
囲碁は(例3-1)の地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒2目、白3目で、白1目勝ち。 純碁は(例3-2)の盤上の石を数えます。 黒10個、白11個で、白1個勝ち。 丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、パスにともなうものだけです。 黒が白石1個、白が黒石2個で、白1個勝ち。 以上より、このケースではどの碁でも同じ判定になりました。 これらの例はあまりにも単純なためにかえって奇妙に感じるかもしれませんが、実際の対局では、気が付かない内にもっと色々な事が起こっているのかもしれません。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |