修正丼碁(ザル碁)
実は、丼碁(ザル碁)のルールをほんのチョット修正することで、純碁の勝敗判定との差違をなくすことができます。 【修正丼碁(ザル碁)ルール】(修正部分のみ) 最後のパスは必ず白がしなければならない。 修正はたったこれだけです。 これはどういう意味かと言うと、黒が第1手目を打つ決まりですから、白は最後の手を打つ決まりにし、黒の手数と白の手数を必ず同数にする為です。ただし、丼碁(ザル碁)ではパスも1手の内に入ります。なぜなら、パスでは盤上に石を置かないだけで、石のやり取りは行われているからです。 石は盤上に有るか、ハマになっているかどちらかですから、黒白の手数が同数であれば盤上の石数の差と、ハマの数の差は常に同数になります。 つまり、純碁と丼碁(ザル碁)は同じ判定結果となるのです。 では、具体的に見てみましょう。 |
|
例1-1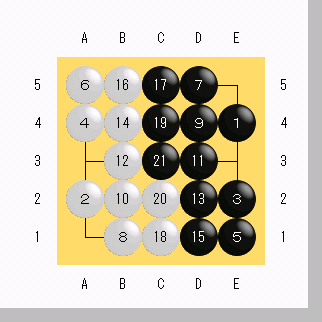 |
前ページと同じ例を使います。 囲碁と純碁は黒21の後白パス、黒パスで終了します。 修正丼碁(ザル碁)はさらに1回白のパスが必要です。 修正丼碁(ザル碁)だけは、パスにともなう石の交換によるハマがあり、黒は白石を2個、白は黒石を1個持っています。 |
囲碁は地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒2目、白2目で、引き分け(持碁)。 純碁は盤上の石を数えます。たとえハマがあっても純碁では関係ありません。 黒11個、白10個で、黒1個勝ち。 修正丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、終局前のパスにともなうものだけです。 黒が白石2個、白が黒石1個で、黒の1個勝ち。 以上より、このケースでは純碁と修正丼碁(ザル碁)が同じ判定で、囲碁の判定が異なります。 |
|
例2-1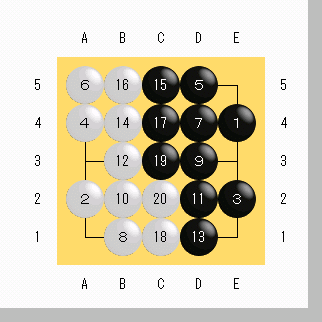 |
これも前ページと同じ例です。 囲碁では白20で終了ですが、純碁と丼碁(ザル碁)は下図のように黒が自陣に打ちます。(下図×印の石) |
例2-2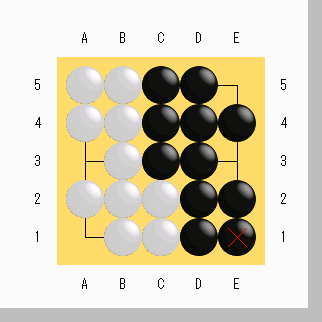 |
純碁はこれでお終い。 修正丼碁(ザル碁)では、次に白がパス(黒に白石を渡す)。続いて黒パス(白に黒石を渡す)。さらに、白パス(黒に白石を渡す)で終了です。 |
囲碁は(例2-1)の地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒3目、白2目で、黒1目勝ち。 純碁は(例2-2)の盤上の石を数えます。 黒11個、白10個で、黒1個勝ち。 修正丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、終局前のパスにともなうものだけです。 黒が白石2個、白が黒石1個で、黒1個勝ち。 以上より、このケースではどの碁でも同じ判定になります。 |
|
例3-1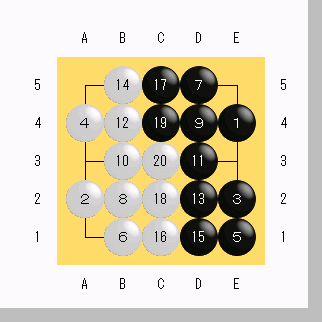 |
これもまた前ページと同じ例です。 囲碁では白20で終了ですが、純碁と丼碁(ザル碁)は続きが有ります。 |
例3-2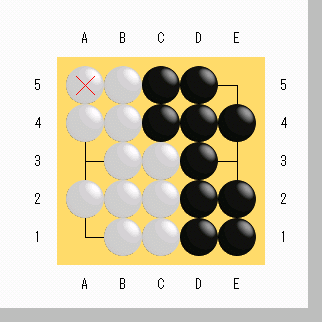 |
黒番ですが打つところが無いのでパス(白に黒石を渡す)です。 次に白が×に打ちます。 純碁はこれでお終い。 修正丼碁(ザル碁)では、次に黒パス(白に黒石を渡す)。続いて白がパス(黒に白石を渡す)で終了です。 |
囲碁は(例3-1)の地を数えます。この場合ハマは無く、眼の分しかありません。 黒2目、白3目で、白1目勝ち。 純碁は(例3-2)の盤上の石を数えます。 黒10個、白11個で、白1個勝ち。 修正丼碁(ザル碁)はハマの数を数えます。このばあい、パスにともなうものだけです。 黒が白石1個、白が黒石2個で、白1個勝ち。 以上より、このケースではどの碁でも同じ判定になりました。 このように純碁と丼碁(ザル碁)は同値にできます。しかし、なんとも無理矢理な感じがしないでもありません。なにもこうまでして結果を同じにする必要はないのではないかと思いましたので、このルールは採用しませんでした。 そもそも例1や例2のとき、なぜ白が最後のパスをしなければいけないのか、その説明を初心者の人にするのはちょっと・・・ねぇ。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |