隅の曲がり四目(補足)
お約束通り、前回書ききれなかった事を幾つか取り上げますが、その前に「隅の曲がり四目問題」を確認しておきます。 隅の曲がり四目問題とは、「一方からは手出しできない形で、他方からは隅の曲がり四目のコウに持ち込める形が終局時点まで残った場合、その部分の死活をどのように判定すべきか、という問題」です。 つまり、前回取り上げた形以外にも同じ様な状況が起こります。そして結果も同様に判定されます。 では次の形をみてみましょう。 |
|
図8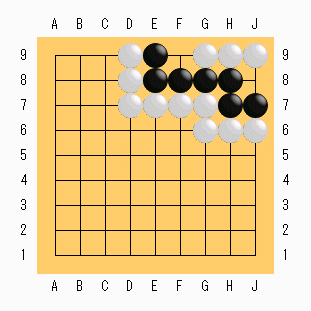 |
左図の形は黒から手出し出来ません。 白からはいつでも J8 に打つことによって隅の曲がり四目からのコウに持ち込む権利があります。 (うっかり F9 に打ってはいけませんよ。黒を活かしてしまいます。) しかし白がコウにする必要がないときは、結局双方手を着けず、終局時点までこの形が残ることになり「黒死」と判定されます。 |
この問題はさらに一般化でき、「隅の曲がり四目」を省くことにより、「一方からは手出しできない形で、他方からはいつでもコウに持ち込める形が終局時点まで残った場合、その部分の死活をどのように判定すべきか、という問題」となります。 つまり、隅以外でも同類の問題は発生する可能性があり、やはり同様な死活判定となります。こうなると「隅の曲がり四目問題」とは言えなくなりますが、問題の本質は全く同じです。 もうだいぶ以前の話ですが、確かトップアマ同士のテレビ対局だったと記憶していますが、盤中央でそのような形が発生し、対局者がこの問題に気が付いているかどうかを解説の坂田先生が心配された場面がありました。 しかしさすがにトップアマらしく、対局者は全く正確に状況を把握していて坂田先生の心配は杞憂に終わりました。 でも、もし一般のアマチュアがそんな局面に出くわしたとしたらトラブルになるかもしれないですねぇ。 如何でしょう、「隅の曲がり四目問題」をご理解頂けたでしょうか。 ちょっと蛇足ですが、違う角度からもう少し考えてみましょう。 |
|
図9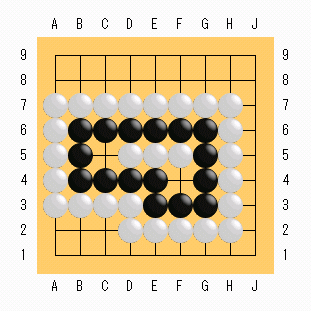 |
左図は図8の形を中央に移動させたものです。 この形は黒白共に手を出せない形、つまりセキです。 双方共に選択権がない平等な状態です。 しかし、図8は白だけが、そのつもりがあればいつでもコウを始められる形です。 つまり、白に選択権がある分だけ、セキよりも白に有利な状態といえます。 図8は、いわば「セキになり損なった形」と言っても良いでしょう。 とは言っても、白は容易にコウを始めませんから、両者が最後まで手を着けずに終局に至るという点ではセキとよく似ています。 そこで問題となるのが、左図のようなセキとは違って図8では黒白の権利のバランスが崩れている点をどう評価するべきか、ということになるわけです。 |
| 旧規約である日本棋院囲碁規約では、「隅の曲がり四目は無条件死」と規定していました。この規定は上記の「権利のアンバランス」を評価した結果だと思いますが、現在の日本囲碁規約ではそのような特別な規定はなく、その代わりより一般化された権利のアンバランスが死活判定の結果に反映するようにルールが定められています。 しかし巷ではいまだに旧規約の「隅の曲がり四目は無条件死」という言葉は健在で、それが正しい意味で使われていれば問題ないのですが、時々とんでも無い思い違いに出会うことがあります。 |
|
本来の隅の曲がり四目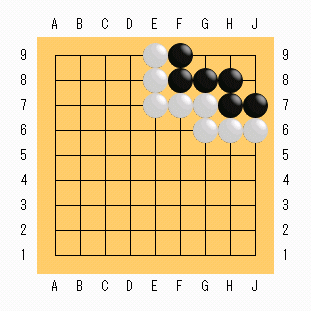 |
左図は本来の隅の曲がり四目ですが、この形を無条件死であると主張する人を稀に見かけます。 この形は、黒無条件死ではありません。黒番なら黒活き、白番ならコウです。 言葉に囚われてゆめゆめ思い違いの無いよう、お気をつけ下さい。 以上蛇足でした。 |
さて、今までは「下図の形が終局までそのまま残っていれば黒死と判定される」と言ってきました。では、下図の形が終局まで維持できないケースと言うのはあるのでしょうか。 次にそのような状況を考えてみましょう。 |
|
図8(再掲)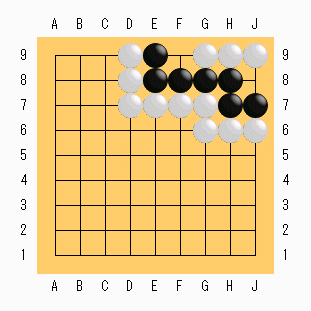 |
この形を維持するには実は条件があります。 その条件とは、一番外側の白石が活きていなければいけないということです。 次図を見て下さい。 |
図10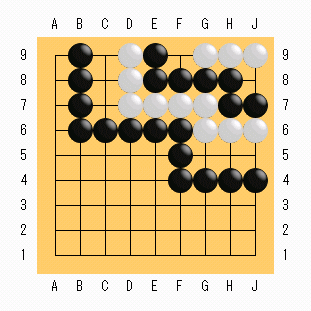 |
白石が取り囲まれています。しかも目を2個持つスペースがありません。 このまま放っておくとこの白石は取られてしまいます。 つまり、図8の形を維持できない状態です。そして、死ぬはずだった黒石が復活してしまいます。 こんな状況になったら、白は J8 に打ってコウに持ち込むより仕方ありません。 |
前回の図5や、今回の図8の形が実戦に現れたら、外側の石の状況に注意を払って下さい。 黒の立場で言えば、隅には直接手を着けられないけれど、外側の白を攻める事で間接的にコウに持ち込めるかもしれません。 白の立場で言えば、外側の白が活きてさえいれば、隅の黒は自動的に死です。 どちらの立場でも外側の石の運命が隅に影響することを忘れてはいけません。 以上で「隅の曲がり四目問題」を終わります。 碁にはこの他にももっと難解な形がいろいろ存在します。でもだからといって碁が難しいものだとは思わないで下さい。なぜならそれらの難しい問題はそれなりの実力が身に付いてからでないと発生しないからです。難解な問題に直面する頃にはそれに見合う実力がちゃんと身に付いていますから安心して下さい。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |