隅の曲がり四目
ある掲示板で「隅の曲がり四目は無条件死か?」について熱い議論が交わされています。このテーマそのものについてはその掲示板にお任せするとして、このサイトは一応囲碁入門をテーマとしていますので、「隅の曲がり四目問題とは何か」という基本的なレベルで扱ってみたいと思います。 囲碁の魅力に取り憑かれ面白くてしょうがない時期、しかしまだ碁盤上で起こる様々な出来事に不思議をいっぱい感じている時期、大抵はそんな頃「隅の曲がり四目問題」に遭遇します。 その時運が良いと的確な解説を受けられ正しい認識を持てるのですが、なかなか運の良い入門者は少ないもので、そもそも解説する人の理解が不十分であったためにとんでもない勘違いをしてしまうケースさえあるようです。私もそんな運の悪い入門者の一人でした。 ということで、出来るだけ分かり易く、そして正確に説明するように心掛けます。 ではまず、言葉の解説から入りましょう。始めに、「曲がり四目」とは・・・ |
|
図1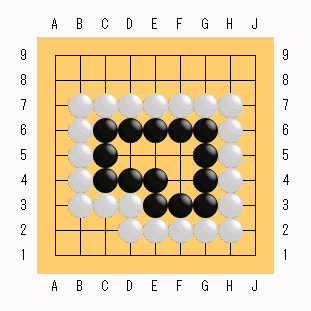 |
左図の黒の形が「曲がり四目」です。 黒石に囲まれている4個の呼吸点がカギ形に曲がった形になっていることから「曲がり四目」と呼ばれます。 この黒はこのままで活きています。 |
図2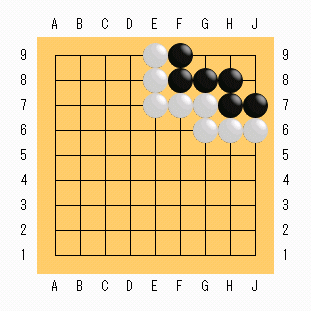 |
その「曲がり四目」が隅に移動したのが左図です。 つまり、この黒の形が本来の「隅の曲がり四目」です。 この形は黒から打てば「黒活き」、白から打てば「コウ」になります。(勝手読み№11参照) 中央の曲がり四目と隅の曲がり四目との大きな違いは、中央では無条件活きであるのに隅では白から打てばコウになってしまうことです。 この点が重要です。 |
図3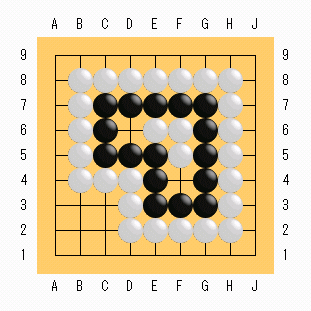 |
さて、ここでちょっと復習です。 左図の形はなんだったでしょうか。 そうです、セキですね。 もし黒が手を出すと全部取られてしまう。 そして白が手を出すと・・・ |
図4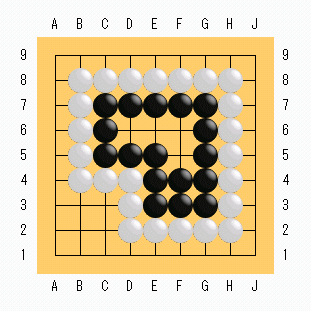 |
この様になります。 これは図1と同じで「曲がり四目」ですから黒の活き形です。 つまり、図3の形からは黒も白も手を出せない。 手を出すと相手の利益なってしまいますから。 |
図5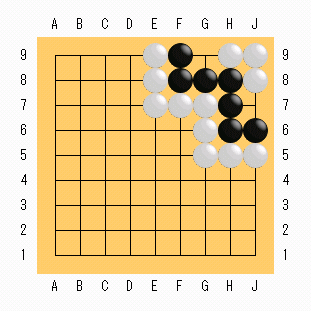 |
では、図3の形を隅に移動するとどうなるか。 中央ではセキでしたが、隅のこの形はちょっと事情が違っています。 黒から手を出せない理屈は図3と同じですが・・・ |
図6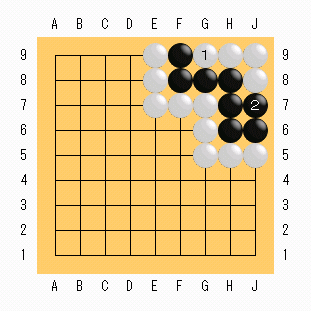 |
白から手を出すと・・・ |
図7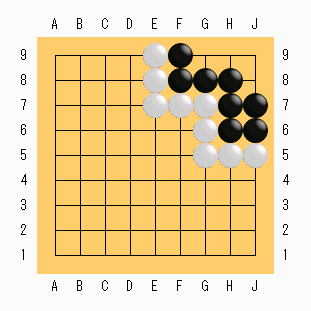 |
この形は図2と同じで「隅の曲がり四目」です。 しかも次は白番です。 と言うことは、コウになります。 白から手を出した場合、中央では黒を活かしてしまい黒の利益に直結しましたが、隅ではコウに出来ますからただちに黒の利益につながるわけではありません。 |
つまり、図5の形は黒からは手を出せないが白からはいつでも隅の曲がり四目からコウに持ち込める権利が残った状態だということです。 さて、図5の形では黒から手を着けないのは当然ですが、白も通常手を着けることはありません。なぜなら黒から何の手段も無い所をわざわざ慌ててコウにして事件を起こす必要もないからです。 で、結局双方とも手を出さず、図5の形が終局までそのまま残るのが普通です。この終局まで残ってしまった図5の形をどのように扱うか、というのがいわゆる「隅の曲がり四目問題」なのです。 |
|
図5(再掲)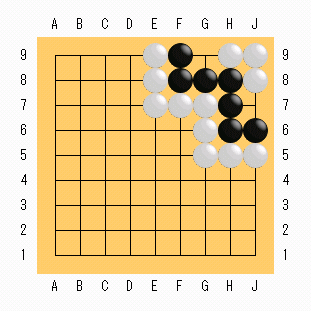 |
このコーナーでは結論のみ書いて終わりにします。 左図の形が終局まで残った場合、日本囲碁規約に従った死活判定によると、「黒石は死」です。 例えどんな強力なコウ立てを黒が持っていようとも、黒石は死と判定されます。 |
この判定について詳細を調べたい方は、日本棋院のホームページから日本囲碁規約を参照して下さい。 ところで、今日このコーナーを読んで頂いた入門者の方は運が良かったのでしょうか、それとも悪かったのでしょうか。 「碁意見盤」にご感想など頂けると嬉しいです。 次回は、「隅の曲がり四目問題」について、今回書ききれなかった大切なことを幾つかテーマにしたいと思います。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |