デイビッドに碁を教えたい
スピルバーグ監督の『A.I.』を観に行ってきました。 この映画の主人公は非常に高度なAI(Artificial Intelligence)を搭載した子供型ロボットです。名前は「デイビッド」。キーワードを入力した人間との間に永遠の愛の絆を持つことを目的に作られています。このデイビッドの運命が映画のストーリーですが、テーマが深いと言うか重いというか、観おわった後しばらく喉が詰まってしまって言葉を発することが出来ませんでした。封切り時期は夏休みを狙ったものだと思いますが、子供にはチョット難しいんじゃないでしょうか。 さて前振りはこの辺にして、今回は碁とAIについて考えてみたいと思います。 (と言っても、たいしたことは書けません) |
|
図1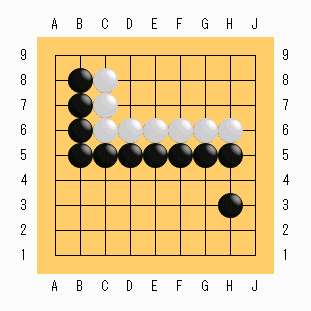 |
本題に入る前に予備知識の確認です。 左図は前回取り上げた一線のハネツギ関連の説明で、最後の方で必ず使われる形です。 上辺の幅が前回のものより随分広くなっています。 前回覚えたこと事が通用するだろうか、という問題です。 |
図2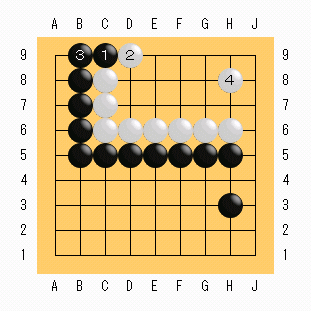 |
前回は黒が1、3と来たら、白4と備えるのが良い、と言うことでした、が・・・。 この図ではどうでしょうか。 |
図3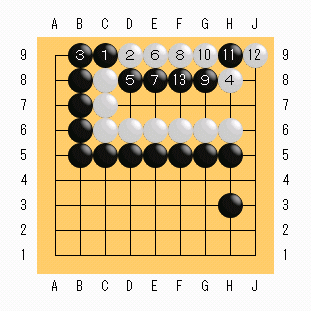 |
これだけ上辺の幅が広いと黒5と切られてしまいます。 黒は9とカケ、11と放り込んで13とアテます。結局白は取られてしまいます。 つまり、ここまで広いと白4では堅くツグ他なかったのでした。 そして黒の立場で言えば、図1は上辺と右辺の両方を先手でハネツグ事が出来る形だということです。 |
図4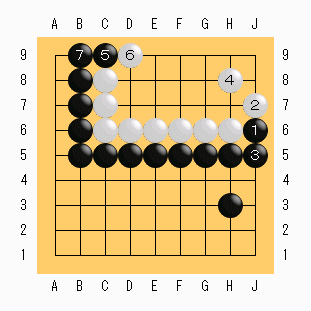 |
ところで、もし右辺のハネツギが先に打って有るとどうなるか、と言うのが左図です。 白は図2にJ7の白石が加わった形です。 この形は黒からD8に切る手が有りません。黒が図3と同じようにやってきても、最後にH7に入ることが出来なくなっています。 つまり、白8が省ける事になります。 黒の立場で言えば、図1の形では上辺のハネツギを先に打たなければいけないと言うことです。右辺のハネツギを先に打つと、上辺が先手で無くなってしまいます。 |
簡単なヨセの問題を一つ作ってみました。 |
|
図5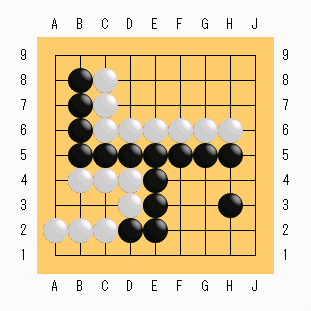 |
いかにも作った図で申し訳ないのですが、左図は黒白共に15手ずつ打ったところで、次は黒番です。 コミ無しでハマも有りません。結果は如何に? |
図6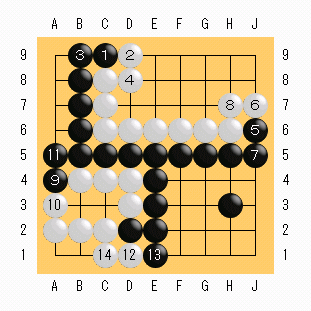 |
左図のような手順のヨセになるでしょう。 黒19目、白18目で黒の1目勝ちです。 中国ルールでは、黒41子で、0.5子勝ちです。 |
図7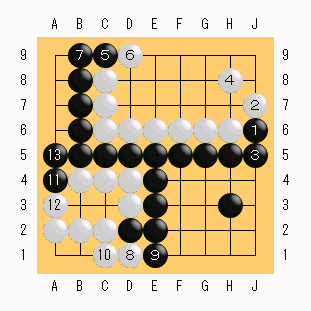 |
もし右辺のハネツギを先に打ってしまうとこの様になります。 手順を誤った為、黒19目、白19目で持碁になってしまいました。 中国ルールでは、図6同様やはり黒41子で、0.5子勝ちです。 日本ルールの方が、一手の価値がより鋭敏に結果に反映する場合があるという事例です。 |
この問題であれば、前回と今回学んだ一線のハネツギの知識を仮に持っていない人でも、図6の手順で打てるかもしれません。しかしそれは偶然であって必然ではありません。 おそらく「囲碁ソフト」も図6の手順で打つだろうと思います。しかしはたして「一線のハネツギ関連知識」を踏まえた上での手順選択かどうか、そこが問題なのです。 最近の囲碁ソフトは定石とか定型とかの知識ベースを持っていて、それとのパターンマッチで手を選択しているという話を聞きました。この程度の問題であればパターンマッチで解決出来るかもしれません。しかしそれだけで人間に勝てるような強いプレーヤーを作ることができるでしょうか。 人間は得た知識を知らず知らずの間に拡張し、他の類似の事例に適用しようと試みます。しかし現状では、それと似たようなことをコンピュータで実現するのはまだまだ難しいようです。 知識を蓄積するだけでなく、得た知識を抽象化して一般化したり連想したり応用したり、そう言った機能を持った強い「囲碁ソフト」は、はたしていつ頃登場してくるのでしょうか。 ところで、デイビッドに搭載されているAIですが、「愛」から生まれた「夢」や「希望」を追い求めるという機能が隠されているんですねぇ。なんともすごいソフトウェアじゃありませんか。でも、ひょっとするとこの機能、最近では本物の人間でも持っていない人が増えているんじゃないかなんて・・・ね。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |