目から鱗
| 碁の魅力の一つとして、「意外性のある発見」を上げることが出来るとおもいます。そして、この発見の経験は尽きることがありません。 入門の時期にはそれなりの驚きを伴う発見が有り、実力が付いてくるとその力に見合った発見を経験することができます。 そういった発見のなかで、比較的入門に近い時期に出会う驚きを今日は取り上げてみましょう。 下の図は、黒番でD4とE4の白2子を取って下さい、という問題です。 |
|
図1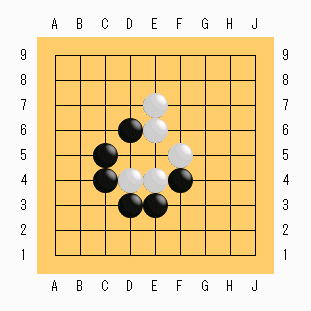 |
知っている人にとってはなんでもない問題ですが、知らない人が自力で正解を得るのは結構難しいのではないでしょうか。 E5に白が打つと白全体がつながってしまいますから、それは防がなければいけません。 |
図2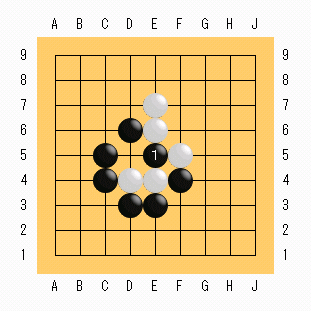 |
つまり黒1と打つしか選択肢はありません。 しかし、この黒1は打ったとたんにアタリになっています。 この様に、アタリになるところに自ら打ち込む発想は、誰かから教えてもらわないとなかなか浮かばないものです。 |
図3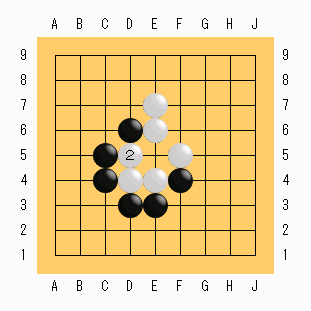 |
当然白2と取られる形です。 初心の内は頭の中に浮かんだこの図の意味が理解できないのです。 石の取り合いに慣れない内は、実際に目の前に石を並べても白3子がアタリになっている事に気が付かないかもしれません。 |
図4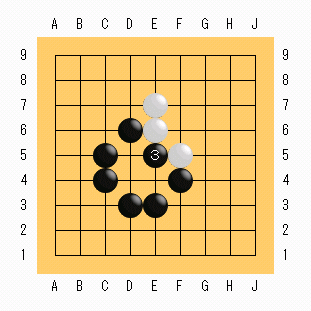 |
黒は左図のように白3子を取ることが出来ました。 この一連のテクニックを「ウッテガエシ」と言います。 「1と打って、2と取らせ、3と取り返し」となることからそう呼ばれているのだと勝手に思っています。 私がウッテガエシを知ったのは、実戦で相手がこの技を使って私の石を取ったときでした。その瞬間何が起こったのかすぐには理解できませんでした。 |
図5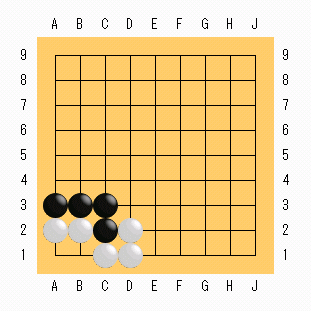 |
隅でも同様の技が使えます。 黒から打って隅の白2子を取って下さい。 もう簡単ですよね。 |
図6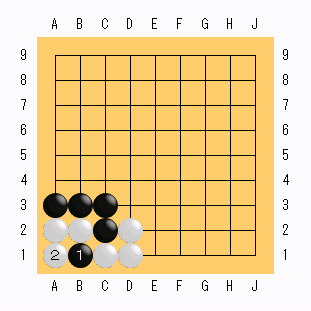 |
黒1と打ち込み、白2と取らせ、再度1の所に黒が打てば隅の白を取ることができます。 これもウッテガエシです。 |
図7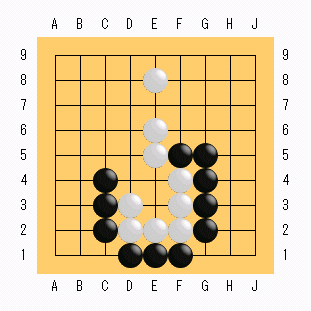 |
こんな形もあります。 黒先で下方の白6子を取って下さい。 |
図8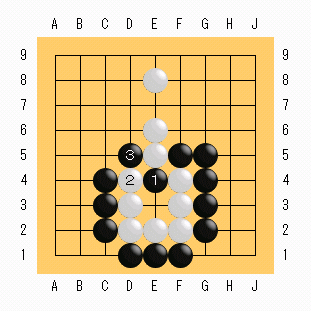 |
上との連絡を絶つには黒1は必然です。 白2とこちら側からつながろうとしますが、 黒3と再度切断します。 これで白は捕まっています。 黒1の石を取ってもその後白の一団が取られてしまうことを確認してください。 これもやはりウッテガエシです。 |
私の固い頭では到底自力でこの技を発見することは出来なかったでしょう。でも、もし自力で発見出来ていたとしたら、もううれしくてたまらなかったでしょう。 さて、次は応用編です。 |
|
図9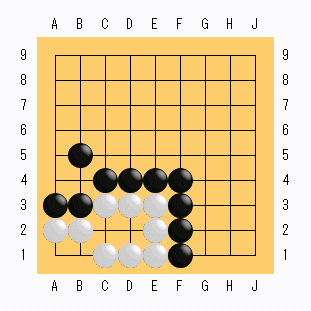 |
この白は2眼を持って活きています。 では、次の図はどうでしょう。 |
図10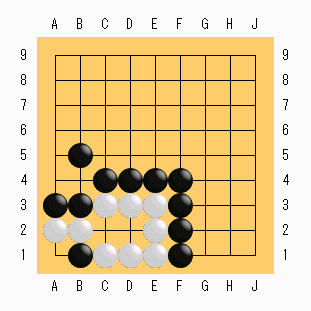 |
上の図と比べると、変なところに黒石が一個有ります。 今黒番として、この白を殺して下さい。 |
図11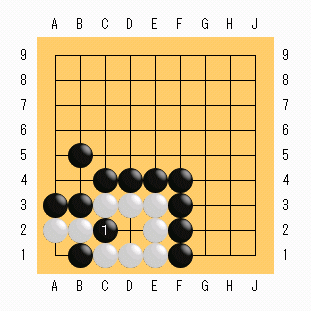 |
この問題も知っている人にとっては簡単なんですが、初めてだとびっくりするかもしれません。 黒1と放り込みます。 これで白は死んでいます。 中の黒石のどちらを取っても、取られたところに打ち返されて白が取られてしまいます。 この図は右も左もウッテガエシということで、 「両ウッテガエシ」といいます。 |
この両ウッテガエシが実戦に現れることは滅多にないでしょう。でも、図9の様な形はたまに見かけます。 図9は完全な活きですが、もし2手続けて打てるとすると図10、11の様に白を仕留めることができます。 えっ、2手続けてなんて打てないって? いやぁ、そんなことはありません。講座で「コウ立て」ってのをやりましたよね。 どこかでコウ争いが起こったときは、その振り替わりとして2手打てるかもしれませんよ。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |