日本囲碁規約考
思いっきり意訳Ⅱ
| 第二条(着手) 対局する両者は、一方が黒石を相手方が白石をもって相互に一つずつ着手することができる。 第三条(着点) 盤上は、縦横一九路、その交点三百六十一であり、石は、第四条に合致して盤上に存在できる限り、交点のうちの空いている点(以下「空点」という)のすべてに着手できる。着手した点を「着点」という。 第四条(石の存在) 着手の完了後、一方の石は、その路上に隣接して空点を有する限り、盤上のその着点に存在するものとし、そのような空点のない石は、盤上に存在することができない。 第五条(取り) 一方の着手により、相手方の石が前条に基づき盤上に存在することができなくなった場合は、相手方のその石のすべてを取り上げるものとし、これを「ハマ」という。この場合、石を取り上げた時点をもって着手の完了とする。 上記第二条から第五条に書かれている事柄は囲碁の基本ルールです。このコーナーを読んで頂いている人は少なくとも私の「囲碁入門やり直し講座」をご理解頂けているはずですので、これらの条文はちょっとばかりややこしい表現にはなっていますが、講座でやった内容と同じであることはお分かり頂けると思います。 ただし一つだけどうしても主張しておきたい私の解釈があります。それは、第五条の最後の部分「石を取り上げた時点をもって着手の完了とする」というくだりについてです。 下図を見て下さい。攻め合いで今は白の手番です。 |
|
図1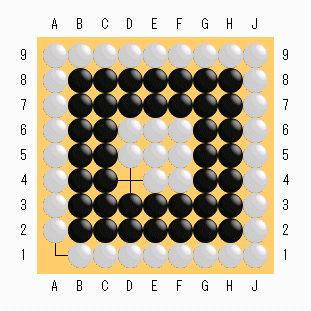 |
黒石白石共に現在D4に「空点を有する」状態であるため盤上に存在しています。(第四条・石の存在) |
図2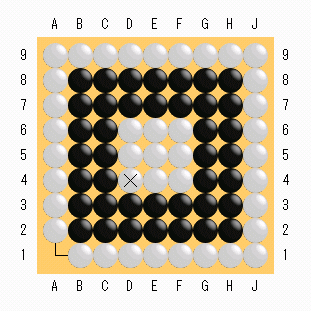 |
しかし、今白番であるため、白は当然×の様に着手し、「黒の石が第四条に基づき盤上に存在することができなくなったため、黒のその石のすべてを取り上げる」ことになります。(第五条・取り) |
図3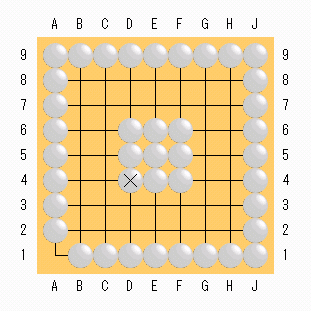 |
その結果左図になり、白の「着手の完了」となり、白×とその一団は「隣接する空点」が出来たので盤上に存在できることになります。(第四条・石の存在) |
さて、盤面が図2の状態から図3の状態になるのに必要な時間はどのくらい掛かるでしょうか。もし私が白番でこの黒石を取り上げるのであれば、盤面を崩さないように注意しながら全部の石を取り上げるのにどんなに急いでもおそらく20秒以上は必要であろうと思います。 ところで第五条の「石を取り上げた時点をもって着手の完了とする」というのはこの20秒後の事を指しているのでしょうか。 私はそうは解釈していません。第四条及び五条の表現は、上図の例のような「双方に共通な唯一の隣接する空点に着手した場合、着手した側の石は盤上に残り他方はハマになる」というルールを規定する為の表現であって、決して取り上げるのに実際に必要な時間の後に着手が完了すると言いたいのではないと考えています。 こんなことを敢えて言うのは、対局時計を使った試合において、大石を仕留めた側が相手の石を取り上げている間に時間切れで負けた、などという話を聞くからです。しかし、これはおかしな事です。石を取り上げる時間を着手の時間に含めるのはどう考えても不合理です。 さらにもっとひどいのは、自分が負けそうになった時わざと相手に自分の大石を取らせるように仕向け、相手の時間切れを狙う輩が居るというのです。そんなのは作戦でもなんでもありません。「盤上での技芸を競う」のとはかけ離れた行為です。 ということで、私はこの部分については妙な解釈が入り込む余地の無い、もう少し工夫した表現に改善すべきではないかと考えています。 次回は、第六条(劫)について考えます。 |
|
| 前ページ | 勝手読みメニュー | 次ページ |